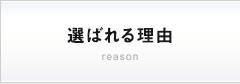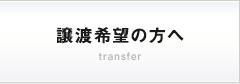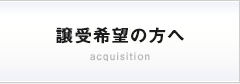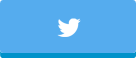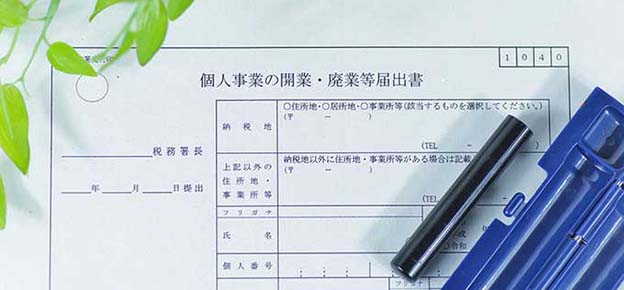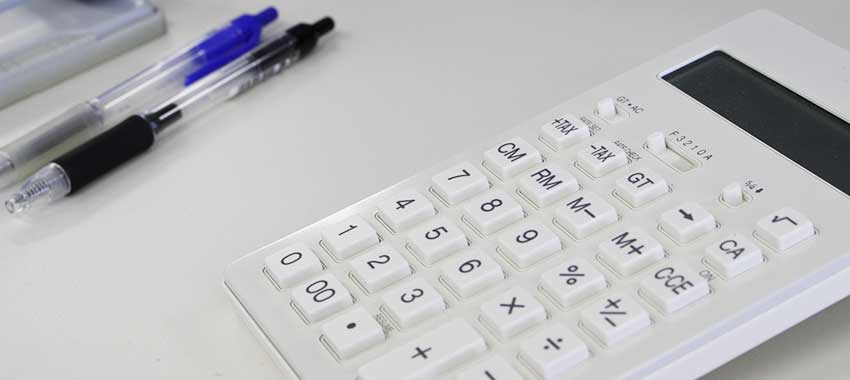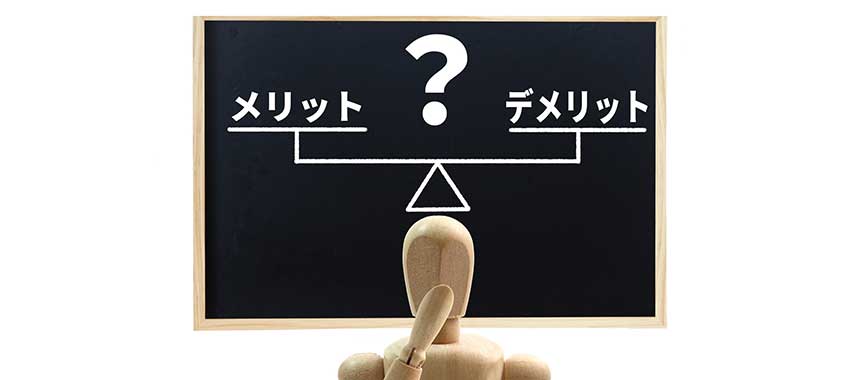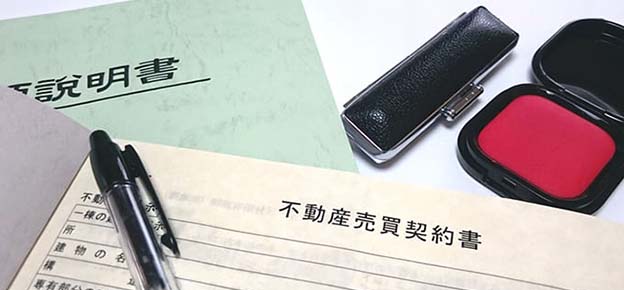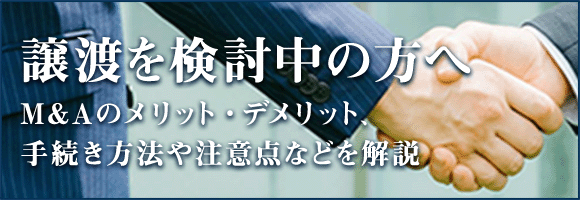- M&A相談センター
- M&Aガイドブック
- 譲渡への第一歩はここから
- 会計事務所・税理士事務所の事業承継の流れや成功させるためのポイントを解説
会計事務所・税理士事務所の事業承継の流れや成功させるためのポイントを解説

更新日:
会計事務所・税理士事務所の事業承継(引き継ぎ)とは
会計事務所や税理士事務所における事業承継とは何か
会計事務所・税理士事務所における事業承継とは、事務所の経営権や財産、そして何より大切な顧客との信頼関係を次世代に引き継いでいく重要なプロセスを指します。一般企業の事業承継と大きく異なる点は、専門的な資格やスキル、長年かけて築き上げた顧客との深い信頼関係が事業の根幹となっていることです。そのため、単なる経営権の移転だけでなく、専門知識やノウハウの伝承、顧客との関係性の維持が特に重要となります。
会計事務所・税理士事務所が直面する承継問題の特徴
会計事務所・税理士事務所特有の承継問題として、以下のような課題が挙げられます。まず、顧客との関係が属人的である点です。長年にわたり築き上げた信頼関係を、いかにして後継者に引き継いでいくかが大きな課題となります。次に、専門的なスキルと経験の継承です。税務や会計の専門知識はもちろん、経営者としての判断力や顧客対応力など、実務経験を通じて培われる能力の伝承が必要不可欠です。さらに、事務所の価値評価の難しさも特徴的です。顧客基盤や人材、ノウハウなど、目に見えない資産の評価が重要となります。
会計事務所・税理士事務所の事業承継方法
事業承継の方法は、大きく3つのパターンに分類されます。
- 第一に、子どもや親族への承継を行う「親族間での事業承継」があります。これは従来から多く見られる形態ですが、後継者となる親族に適性があるかどうかの見極めが重要です。
- 第二に、従業員や外部の税理士・会計士への承継を行う「親族以外への事業承継」です。この方法は、能力や意欲のある人材を広く候補者として検討できる利点があります。
- そして第三に、近年増加している「M&Aによる事業承継」です。この方法では、経営資源の効率的な活用や事業の発展性を見据えた戦略的な承継が可能となります。特にM&Aは、後継者不在の課題を解決するだけでなく、事務所の価値最大化や新たな成長機会の創出にもつながる可能性があり、戦略的な選択肢として注目を集めています。
このように、会計事務所・税理士事務所の事業承継は、単なる事業の引き継ぎにとどまらず、専門性の高いサービスの継続性を確保する重要な経営判断といえます。
事業承継の進め方と具体的な流れ
それぞれの事業承継方法について、実務的な視点から具体的な進め方とポイントを解説していきます。特に重要なのは、どの方法を選択する場合でも、早期からの計画的な準備と実行が成功の鍵となることです。
1. 親族間での事業承継の流れと注意点
親族への承継は伝統的な方法ですが、準備不足による失敗も少なくありません。計画的な準備と実行が重要です。
後継者の適性評価と育成(3~5年前)
まず後継者となる親族の資質や意欲を客観的に評価することから始めます。税理士資格の有無だけでなく、経営者としての資質や顧客対応力なども重要な判断基準となります。資格取得支援や実務経験の機会提供など、具体的な育成計画を立てて実行していきます。
経営権と財産の移転計画策定(2~3年前)
株式や財産の移転方法、時期について具体的な計画を立案します。税務上の影響を考慮しながら、段階的な移転を検討するのが一般的です。この際、他の相続人への配慮も必要不可欠です。
個人保証・負債の処理(2~3年前)
事業承継では資産だけでなく、個人保証や負債の処理も重要な検討事項となります。特に個人保証は後継者に大きな負担となる可能性があるため、早期からの対策が必要です。経営者保証ガイドラインを活用することで、事業の安定性や個人資産と事業資産の明確な分離などの要件を満たせば、個人保証を引き継がずに済む可能性があります。このため、承継の2~3年前から、経営者保証解除に向けた事業基盤の整備を進めることが望ましいでしょう。
顧客引継ぎプロセスの実施(1~2年前)
重要顧客から段階的に引継ぎを開始します。まずは現経営者の補助的な立場で同席するところから始め、徐々に主担当としての対応に移行していくのが効果的です。
2. 親族以外への事業承継の流れと注意点
従業員や外部の専門家への承継は、能力重視で後継者を選定できる利点があります。
後継者候補の選定と交渉(3~5年前)
社内の優秀な従業員や、外部の税理士・会計士から後継者候補を選定します。候補者との綿密な協議を通じて、経営理念の共有や条件面での合意を図ります。
権利移転と価格の決定(2~3年前)
事務所の価値評価を行い、株式譲渡価格や支払条件について合意を形成します。分割払いなど、後継者の資金負担に配慮した柔軟な対応を検討することも重要です。
個人保証・負債の整理(2~3年前)
親族以外への承継の場合、個人保証や負債の処理は特に慎重な対応が求められます。経営者保証ガイドラインを活用し、事業の安定性確保や資産の明確な分離を進めることで、後継者の個人保証負担を軽減できる可能性があります。特に外部からの承継の場合、この部分がネックとなって承継が進まないケースも多いため、早期からの計画的な対応が重要です。
段階的な権限委譲の実施(1~2年前)
合意された計画に基づき、徐々に経営権と業務権限を移譲していきます。特に顧客対応については、スムーズな引継ぎのために慎重な進行管理が必要です。
3. M&Aによる事業承継の流れと注意点
M&Aによる承継は、事業の発展性や価値最大化を見据えた戦略的な選択肢として注目されています。
事務所の価値評価と売却準備(1年半~2年前)
顧客基盤、人材、業務プロセスなど、事務所の資産価値を多角的に評価します。特に、将来の収益性に影響を与える要因について詳細な分析が重要です。売却に向けた資料作成や体制整備も並行して進めます。
買収先の選定と条件交渉(1年前)
M&Aアドバイザーの支援を受けながら、最適な買収先を探索します。規模や地域性、業務の専門性など、様々な観点から相乗効果が期待できるパートナーを選定します。
デューデリジェンスと最終契約(6ヶ月前)
選定された買収先による詳細な調査を経て、最終的な契約条件を詰めていきます。この段階では、顧客情報の取り扱いや従業員の処遇など、細かな点まで明確な合意が必要です。特に重要なのは、クライアントへの影響を最小限に抑えるための移行計画の策定です。
以上のように、各承継方法にはそれぞれ特徴的な進め方とタイムラインがあります。特にM&Aによる承継は、専門的なサポートを受けながら進めることで、より戦略的かつ効果的な事業承継が実現できる可能性があります。
会計事務所の事業承継のメリット
事業承継・M&Aを活用すると、単に”次の経営者を見つける”だけにとどまらず、事務所の価値や関係性を未来へ引き継ぎながら経営者・従業員・顧客すべてにメリットをもたらします。それぞれの視点から主なメリットを見ていきましょう。
後継者不在問題の解決
身内や所内に適切な後継者がいない場合でも、外部譲渡によって事務所の存続が可能になります。これにより、廃業によるクライアントへの影響や従業員の雇用問題を回避できます。特に近年は少子化の影響もあり、この問題に直面する事務所が増加傾向にあります。計画的な事業承継により、長年築き上げた事務所の価値を維持しながら、円滑に次世代へとバトンを渡すことができるのです。
従業員の雇用と安定の維持
雇用契約・待遇を引き継ぐ形で承継を行えば、人材の流出を防ぎやすくなります。特に税務・会計の専門知識を持つ人材は市場価値が高く、事業承継の不確実性から離職するケースも少なくありません。計画的な承継プロセスを通じて従業員に将来の見通しを明確に示すことで、優秀な人材の流出リスクを大幅に軽減し、組織の安定性を維持することができます。また、より大きな組織と統合することで、従業員のキャリアパスが広がるケースもあります。
取引先・顧客関係の継続
既存の顧問先や提携先との信頼関係をそのまま保持することで、売上の急減を回避できます。適切な引継ぎプロセスを経ることで、クライアントの不安を最小限に抑え、高い顧客維持率を実現できます。特に長期的な関係構築が重要な税務・会計業界では、この継続性が事務所の安定経営に直結します。また、承継先の組織がより多様なサービスを提供できる場合、既存顧客に対してより総合的な支援が可能になるという付加価値も生まれます。
現経営者の専門的関与の継続
引退後もシニアアドバイザーや非常勤税理士として関与することで、知見を生かしつつ段階的にリタイアすることが可能になります。これにより、急激な環境変化による心理的負担を軽減しながら、長年培った専門知識を活かし続けることができます。クライアントにとっても急激な担当者変更の不安が軽減され、新旧経営者の協力体制による質の高いサービス提供が継続されるメリットがあります。特に複雑な案件や長期的な顧問関係にある重要クライアントについては、このような段階的な移行が信頼関係維持に大きく貢献します。
資産価値の実現と経済的安定
株式譲渡・事業譲渡時に得た対価を老後資金や新規投資に充当することができます。特に個人事業主として長年経営してきた場合、退職金制度がないケースも多く、事業価値を適正に評価して譲渡することで、経営者の老後の経済的安定を確保できます。また、この資金を新たな事業展開や投資に活用することで、第二の人生を充実させる選択肢も広がります。事業承継・M&Aを通じて、長年の努力で築き上げた無形資産を含む事業価値を適正に評価し、経済的リターンとして実現できることは大きなメリットといえるでしょう。
ブランドとノウハウの承継
長年培った事務所ブランド、業務フロー、職員教育ノウハウを一体で引き渡せるため、後継側は早期に運営を軌道に乗せやすくなります。特に地域密着型の事務所の場合、地域での信頼・評判は何十年もかけて築かれたかけがえのない資産です。これを承継することで、新たなスタートでは得られない市場優位性を引き継ぐことができます。承継側にとっては、すでに確立された信頼とブランド力を活用できるため、新規開業に比べて格段に早く事業を安定させることが可能になるのです。
これらのメリットを理解したうえで早期に計画を立てることで、「誰にどのように引き継ぐか」という選択肢を広げ、事務所の価値を最大化できます。特に事務所の将来を見据えた戦略的な視点から事業承継を捉えることで、単なる引継ぎ以上の価値創造につながるでしょう。
会計事務所の事業承継のデメリット・注意点
事業承継には多くのメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に認識し、適切な対策を講じることが成功への重要なステップとなります。
準備開始の遅れによる承継失敗リスク
事業承継は複数年をかけて計画的に進めるべきプロセスです。特に会計士・税理士事務所の場合、顧客との関係性の引継ぎや専門性の伝承に時間を要するため、準備の遅れは深刻な問題につながります。経営者の突然の体調不良や引退の意向が生じた際に準備不足だと、急ごしらえの承継プランしか選択できず、事務所の価値が大幅に毀損するケースも少なくありません。対策としては、少なくとも5年前から具体的な準備を始め、複数のシナリオを想定した計画立案が重要です。
不適切な後継者・譲受先選定によるトラブル
後継者や譲受先の選定を誤ると、承継後に様々な問題が発生する可能性があります。特に親族承継の場合、経営能力や専門性よりも親族関係を優先すると、事務所の競争力低下や従業員の離職を招くことがあります。また、M&Aによる承継では、文化や経営理念の不一致が顕在化し、統合後の運営が円滑に進まないケースも見られます。対策としては、客観的な基準に基づく候補者評価や、譲受先との十分な対話を通じた相性確認が不可欠です。特にM&Aでは、単に条件面だけでなく、顧客サービスに対する考え方や従業員への対応方針なども重要な判断材料となります。
顧客離れの可能性
会計士・税理士事務所の最大の資産は顧客基盤ですが、事業承継に伴い顧客が離れるリスクは常に存在します。特に、顧問先との関係が現経営者の個人的な信頼関係に依存している場合、承継によって関係性が希薄化し、契約解除につながる可能性があります。こうした顧客離れは、譲渡価格の算定基準となった収益予測を大きく狂わせることにもなりかねません。対策としては、段階的かつ計画的な顧客引継ぎが重要です。主要顧客に対しては個別面談の機会を設け、新体制への移行について丁寧に説明するとともに、一定期間は現経営者も関与を続けるなどの配慮が効果的です。
売却価格・相場の認識不足
特にM&Aによる承継を検討する場合、事務所の適正な価値評価と市場相場の理解が不可欠です。過大な価格設定は買い手不在の状況を生み、過小評価は長年の努力で築いた事業価値を適正に回収できない結果となります。会計士・税理士事務所の場合、単純な財務指標だけでなく、顧客基盤の安定性、スタッフの質、業務の標準化・システム化の程度など、多角的な視点での評価が必要です。対策としては、専門的な知見を持つM&Aアドバイザーの活用と、複数の評価手法を組み合わせた総合的な価値算定が有効です。
税務上の負担
事業承継に伴い、贈与税や譲渡所得税などの税負担が発生する可能性があります。特に個人事業主の場合、「のれん」など無形資産の評価が難しく、想定外の税負担が生じるケースも見られます。また、法人と個人の間での事業譲渡では、課税関係が複雑化することも多いです。対策としては、早期からの税務プランニングが重要です。親族内承継であれば「事業承継税制」の活用検討、M&Aによる承継では適切な譲渡スキームの構築など、税理士としての専門知識を活かした最適化が必要です。特に個人事業主の場合は、承継前に法人成りを検討するなど、承継に有利な体制を整えることも一つの選択肢となります。
法的手続きの複雑さ
事業承継、特にM&Aでは様々な法的手続きが必要となります。契約書の作成、許認可の引継ぎ、従業員の雇用契約変更など、専門的な法務知識が求められる場面が多く、手続きの遅延やミスが承継プロセス全体に影響を及ぼすことがあります。さらに、法人形態でない場合は事業譲渡となり、個別資産の移転手続きが煩雑になることも考慮すべきです。対策としては、専門家チームの組成が有効です。会計・税務の専門家である自身の知見に加え、M&A専門のアドバイザーや弁護士など、異なる専門性を持つ専門家との連携により、法的リスクを最小化することができます。
これらのデメリットやリスクは、適切な準備と専門家の支援により大幅に軽減することが可能です。重要なのは、リスクの存在を認識した上で、計画的かつ戦略的に対策を講じていくことです。特に会計士・税理士という専門職の事業承継においては、専門的な知見を持つアドバイザーの支援を受けることが、こうしたリスクの回避に大きく貢献します。
会計事務所の事業承継の相場・価値評価
事業承継、特にM&Aによる承継を検討する際に、多くの経営者が抱える疑問が「自分の事務所はいくらで譲渡できるのか」という点です。会計士・税理士事務所の価値評価には特有の考慮点があり、適切な評価手法の選択と専門家の知見が不可欠となります。
会計事務所の価値を決める主な要因
会計士・税理士事務所の価値は、複数の要素により構成されています。顧問先の数と質が最も重要な要素であり、長期契約を結んでいる優良顧客の存在や、顧問料の安定性は高評価につながります。次に、収益力と収益構造が挙げられます。安定した顧問料収入に加え、決算申告業務や自計化支援など、多様なサービスラインを持つ事務所は高い評価を得やすいでしょう。また、人材の質と組織体制も重要です。有資格者の在籍状況や、経営者に依存しない組織的な運営体制が整っている事務所は、承継後の事業継続性が高く評価されます。さらに、業務プロセスのシステム化・標準化の程度も、事業価値に大きく影響します。
一般的な企業価値算出方法と会計事務所への適用
企業価値の算出方法としては、主に以下の3つのアプローチがあります。
インカムアプローチ(収益還元法)
将来の収益や利益、キャッシュフローに基づいて企業価値を算出する方法です。会計士・税理士事務所の場合、安定した収益基盤を持つケースが多いため、DCF法(割引キャッシュフロー法)やEBITDA倍率法が用いられることが一般的です。特にM&Aでは、「EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)の3〜5倍」を基準とした価格算定が行われるケースが多く見られます。ただし、個人事業主の場合は、経営者の人件費を適正に反映するなどの調整が必要となります。
マーケットアプローチ(市場比較法)
類似企業の取引事例や市場価格を参考に企業価値を算出する方法です。会計士・税理士事務所の場合、売上高倍率や顧問料収入倍率が参考指標となることが多いです。一般的な相場としては、「年間売上高の0.8〜1.2倍」や「月額顧問料収入の12〜24ヶ月分」が譲渡価格の目安として言われていますが、事務所の規模や収益性、地域性などにより大きく変動します。大都市圏の大規模事務所では倍率が高くなる傾向にあり、地方の小規模事務所では低めの評価となることが多いでしょう。
コストアプローチ(資産評価法)
企業が保有する資産から負債を差し引いた純資産価値をベースに企業価値を算出する方法です。会計士・税理士事務所の場合、有形資産の占める割合が低く、のれん価値や顧客基盤などの無形資産が大きな割合を占めるため、単純な純資産評価では事業価値を適切に反映できないことが多いです。ただし、事務所が所有する不動産や高額な設備などがある場合は、これらの資産価値も考慮する必要があります。
事務所規模と価値評価の関係
会計士・税理士事務所の価値評価は、事務所の規模によっても評価アプローチや重視される要素が異なってきます。ただし、具体的な数値や倍率は個別の状況により大きく変動するため、以下の点は一般的な傾向として参考程度にとどめておくことが重要です。
- 小規模事務所:個人事業主や少人数の事務所では、経営者個人の顧客関係や専門性に価値が集中していることが多く、いかに円滑に顧客関係を移転できるかが評価の鍵となります。また、業務の標準化やマニュアル化の程度も重要な評価ポイントとなります。
- 中規模事務所:組織としての体制が整い始める規模では、安定した顧問先基盤に加えて、専門人材の充実度や業務プロセスの効率化、サービスの多様性なども価値評価に大きく影響します。経営者への依存度が低く、組織的な運営ができている事務所ほど評価は高まる傾向にあります。
- 大規模事務所:一定規模以上の事務所では、組織的な経営基盤や成長性、特定分野での専門性や独自サービスの展開など、事業としての発展可能性も重要な評価要素となります。また、デジタル化やIT投資の状況なども将来性を左右する要因として注目されます。
事務所価値の算定方法としては、収益還元法(EBITDA倍率法やDCF法)を基本としながらも、顧問料収入の安定性や顧客基盤の質、人材の充実度などを総合的に加味して評価されるのが一般的です。相場感については、業界専門のM&Aアドバイザーに相談することで、直近の類似事例や市場動向を踏まえた現実的な価格レンジを把握することが可能です。
事業承継を成功させるためのポイント
会計士・税理士事務所の事業承継を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。特に専門性の高いサービス業であるからこそ、人材と顧客との関係性に焦点を当てた準備が不可欠です。
事業承継の目的・優先事項を明確化する
事業承継を検討する際、まず重要なのは経営者自身が「何を実現したいのか」という承継の目的と優先順位を明確にすることです。例えば、長年共に働いてきた従業員の雇用継続を最優先するのか、事務所の更なる事業拡大や発展の可能性を重視するのか、あるいは経営者自身の引退後の経済的安定のために売却益の最大化を図るのかなど、経営者によって重視する点は異なります。
これらの優先順位が明確になっていないと、承継の方法選択や条件交渉の過程で判断基準がブレてしまい、結果として理想とは異なる承継結果となるリスクがあります。例えば、「高額での売却」と「従業員の処遇維持」は時に相反する場合もあるため、どちらを優先するかの判断が必要です。優先順位を明確化しておくことで、譲れない条件と妥協可能な条件の線引きができ、交渉においても一貫した姿勢を保つことができます。
また、家族や親族、従業員など、承継に関わる関係者との間で、これらの目的や方向性について早期から対話を重ね、共通理解を形成しておくことも重要です。特に親族内承継の場合、経営理念や事業への想いを共有していないと、承継後に方針の不一致が表面化し、事業の継続性に影響を及ぼすこともあります。M&Aによる事業承継においても、買い手との間で経営理念や顧客サービスに対する考え方について十分な対話を行い、相互理解を深めることが円滑な統合の鍵となります。
後継者育成とスタッフ管理
後継者の育成は、事業承継の成否を左右する最も重要な要素の一つです。専門的な知識やスキルの習得はもちろんのこと、経営者としての資質を養うことも必要不可欠です。
後継者に求められる能力開発
経営者として必要な判断力や決断力を養うため、段階的に権限を委譲していくことが重要です。まずは日常業務の管理から始め、徐々に経営判断が必要な場面を任せていきます。また、財務管理や人事管理など、経営全般に関する知識も計画的に習得させることが望ましいでしょう。
既存スタッフとの関係構築
後継者が新しい経営者として認められるためには、既存スタッフとの良好な関係構築が欠かせません。スタッフの意見に耳を傾け、コミュニケーションを密にとることで、円滑な体制移行が可能となります。特に、ベテラン従業員の知識やノウハウを活用する体制づくりは、事務所の継続的な発展に重要です。
事業承継計画を早期に立案すること
事業承継の成功には、5年から10年という長期的な視点での計画立案が不可欠です。早期の準備により、様々なリスクを軽減し、円滑な承継を実現することができます。
具体的なタイムラインの設定
承継までの期間を具体的なフェーズに分け、各段階での目標と達成事項を明確にします。特に、後継者の育成期間、権限移譲の時期、財務や法務面での整理など、重要なマイルストーンを設定することが有効です。
計画の定期的な見直し
事業環境や状況の変化に応じて、計画を柔軟に見直すことも重要です。半年に一度程度、進捗状況を確認し、必要に応じて計画を修正することで、より実効性の高い承継を実現できます。
顧客・クライアントへの周知と信頼関係の維持
会計士・税理士事務所にとって、顧客との信頼関係は最も重要な資産です。事業承継に際しては、この信頼関係を維持・強化することに特に注力する必要があります。
段階的な引継ぎプロセス
顧客との関係性を維持するためには、急激な変更を避け、段階的な引継ぎを行うことが重要です。まずは現経営者と後継者が共に顧客を訪問し、徐々に後継者が主体的な対応を行うようにしていきます。この際、各顧客の特性や要望に応じて、きめ細かな対応を心がけることが大切です。
コミュニケーション戦略の立案
承継に関する情報は、顧客に対して計画的かつ戦略的に開示していく必要があります。特に重要顧客に対しては、個別に説明の機会を設け、今後のサービス提供体制について丁寧な説明を行います。また、事務所全体としての対応方針や体制変更について、文書やニュースレターなどを通じて適切に情報発信を行うことも効果的です。
これらのポイントは、特にM&Aによる事業承継を検討する場合にも重要な判断材料となります。M&Aの場合、買収側の体制や方針との整合性を図りながら、これらの要素を慎重に検討していく必要があるでしょう。
会計士・税理士事務所の事業承継はどこに相談すべきか?
専門家として日々アドバイスを提供する立場にある会計士・税理士であっても、自身の事務所の事業承継については、客観的な視点と専門的なサポートが必要です。適切な相談先を選ぶことが、円滑な事業承継の第一歩となります。
まずは事業承継に精通したアドバイザーを把握しよう
事業承継、特に会計事務所や税理士事務所の承継に関しては、業界特有の課題や注意点が数多く存在します。そのため、単なる一般的な事業承継の知識だけでなく、会計事務所特有の価値評価や顧客資産の承継などについて深い知見を持つアドバイザーを見つけることが重要です。特にM&Aによる承継を検討する場合は、業界に精通したM&A専門家のサポートが不可欠となります。
M&Aアドバイザーの選び方とポイント
M&Aによる事業承継を検討する場合、以下のような点に注目してアドバイザーを選定することが望ましいでしょう。
業界での実績と専門性
会計士・税理士事務所のM&Aには特有の考慮点があるため、業界での豊富な実績を持つアドバイザーを選ぶことが重要です。特に、M&A相談センターなどの専門機関は、会計事務所の事業承継に関する豊富な知見と実績を有しており、最適な選択肢の一つとなります。
提供されるサービスの範囲
単なるマッチングだけでなく、事業価値評価から交渉支援、PMI(経営統合後の支援)まで、包括的なサービスを提供できる機関を選択することが望ましいです。特に、顧客基盤の評価や従業員の処遇など、専門性の高い事務所特有の課題にも対応できる体制を持っているかどうかが重要なポイントとなります。
公的支援・各種補助制度の活用
事業承継を進める上で、様々な公的支援や補助制度を活用することができます。
主な支援制度と活用のポイント
事業承継・引継ぎ支援センター(中小企業庁)では、専門家による無料相談や、マッチング支援などのサービスを提供しています。初期の相談や情報収集に特に有効です。
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継に関連する経費の一部を補助する制度です。専門家への相談費用やシステム統合費用などが対象となります。
経営革新等支援機関では、承継計画の策定支援や金融機関との調整など、実務的なサポートを受けることができます。
地方自治体や商工会議所では、地域特性に応じた支援メニューを提供しており、地域に根ざした事務所の承継には特に有効です。
相談先を選ぶときに押さえておくべき視点
相談先を選定する際は、以下の点を特に重視することが重要です。
専門性と実績の確認
会計士・税理士事務所の事業承継には特有の課題があるため、業界での実績や専門性を十分に確認します。特にM&Aを検討する場合は、M&A相談センターのような専門機関を活用することで、より適切なアドバイスと支援を受けることができます。
サポート体制の充実度
初期相談から実行支援まで、一貫したサポートを受けられる体制があるかどうかを確認します。特に、M&Aによる承継の場合は、買い手の選定から条件交渉、さらには統合後のフォローアップまで、包括的なサポートが必要となります。
このように、適切な相談先を選択することは、事業承継の成功に大きく影響します。特にM&Aによる承継を検討する場合は、M&A相談センターのような専門機関の活用を積極的に検討することをお勧めします。
税理士・会計事務所のM&A事例
事業承継の問題を抱える税理士・会計事務所では、M&Aが有効な解決策となる場合があります。以下、実際に成功した3つの事例をご紹介します。
事例①: 後継者不足に悩む60代所長の決断
事務所規模: 年商3億円超
相談者: 60代の税理士所長
課題: 息子が後継者候補だがまだ若く、ベテラン従業員も高齢で不安を抱えていた。
解決策: 事業規模に合ったK税理士法人を譲受先として提案し、所長が譲渡後も関与しながらスムーズな移行を実現。
事例②: 病気による顧客流出…友人の支援で実現したM&A
事務所規模: 小規模税理士事務所
相談者: A税理士(所長)& 友人税理士S
課題: 所長の体調不良により顧問先の半数が離脱し、廃業寸前。
解決策: 友人である税理士SがM&Aを提案し、適切な譲渡条件を設定。経営の厳しい状況でも譲渡を成功させ、事務所の存続を実現。
事例③: 90歳の所長の入院を機に、息子が選んだM&A
事務所規模: 中規模事務所
相談者: 副所長A氏(息子)
課題: 90歳の父が入院。息子は所長資格がなく、事業の存続に悩んでいた。
解決策: A氏と顧問先をそのまま受け入れるJ税理士法人を譲受先に選定し、スムーズな事業承継を実現。
まとめ
会計士・税理士事務所の事業承継は、専門性の高いサービスと顧客との信頼関係を次世代に引き継ぐ重要な経営課題です。本記事で解説した内容の要点を以下にまとめました。
- 早期計画が成功の鍵:事業承継は5〜10年単位の長期的な視点で準備を進めることが不可欠です。特に顧客との信頼関係や専門知識の移転には十分な時間が必要となります。
- 自社に最適な承継方法の選択:親族承継、従業員承継、M&Aと、それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。事務所の状況や目標に合わせた最適な手法を選ぶことが重要です。
- 承継の目的と優先順位の明確化:従業員の雇用維持を重視するのか、事業の発展性を重視するのか、経済的リターンを優先するのかなど、経営者自身の価値観に基づいた優先順位を整理することが必要です。
- 後継者の計画的育成:専門知識の習得はもちろん、経営者としての判断力や顧客対応力を段階的に養成することが、円滑な事業承継の要となります。
- 顧客関係の維持が最重要:会計士・税理士事務所の最大の資産は顧客との信頼関係です。段階的な引継ぎプロセスと戦略的なコミュニケーションにより、この関係を維持することが事業価値の保全につながります。
- 事業価値の適正評価:特にM&Aを検討する場合、顧客基盤の質や組織体制、業務の標準化など多角的な要素を考慮した適切な価値評価が重要です。
- デメリット・リスクへの対策:顧客離れや価格設定の誤り、税務上の負担など、事業承継に伴うリスクを事前に認識し、適切な対策を講じておくことが成功への近道です。
- 専門家の支援を活用:事業承継、特にM&Aは専門性の高い分野です。早い段階から業界に精通した専門家のアドバイスを受けることで、より戦略的かつ効果的な承継が実現できます。
- 時代の変化に対応した発展的承継:単なる経営権の移転ではなく、事務所の持続的発展につながる承継を目指しましょう。デジタル化の進展や顧客ニーズの多様化など、時代の変化に対応した新たな価値創造を見据えた承継計画が求められています。
事業承継は経営者にとって一生に一度の大きな決断です。特に会計士・税理士事務所では、長年かけて築き上げた顧客との信頼関係や専門性の高いサービスをいかに継続していくかが大きな課題となります。本記事でご紹介したポイントを参考に、計画的かつ戦略的に事業承継を進めていただければ幸いです。
事業承継に関する具体的なご相談や疑問点がございましたら、会計士・税理士事務所の事業承継に豊富な実績を持つM&A相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門アドバイザーが、あなたの事務所に最適な承継プランをご提案いたします。
会計士・税理士事務所の事業承継に関するよくある質問
事業承継の準備はいつから始めるべきですか?
理想的には事業承継の5〜10年前から準備を始めることをお勧めします。会計士・税理士事務所の場合、顧客との信頼関係の移転や後継者の専門的スキル習得には十分な時間が必要です。特に親族内承継の場合は資格取得のための期間も考慮する必要があります。突発的な事態(健康問題など)に備え、早期から複数のシナリオを想定した計画を立てておくことが重要です。
会計事務所の事業承継でM&Aと親族承継はどちらが良いのでしょうか?
どちらが良いかは事務所の状況や経営者の優先事項によって異なります。親族承継は理念や価値観の継続性が高く、長期的な視点での経営が期待できますが、適切な後継者がいないケースも多いです。一方M&Aは、適切な買い手を見つけることで事業の発展や経済的リターンの最大化が期待できます。重要なのは、自社の状況(後継者の有無、従業員構成、事業規模など)と経営者自身の優先事項(従業員の雇用維持、経済的リターン、事業の発展性など)を踏まえて判断することです。
事業承継時に顧客が離れるリスクをどう防げばよいですか?
顧客離れを防ぐためには、以下の対策が効果的です。まず、段階的な引継ぎプロセスを実施し、現経営者と後継者が共に顧客を訪問する期間を設けることで、信頼関係を徐々に移転します。次に、丁寧なコミュニケーションを心がけ、特に重要顧客には個別に承継計画を説明し、新体制でのサービス内容や担当者について明確に伝えます。また、承継後も一定期間は現経営者が顧問やアドバイザーとして関与することで、顧客の安心感を高めることができます。さらに、サービス品質の一貫性を保つための業務マニュアル整備も重要な対策となります。
事業承継・M&Aにかかる期間はどれくらいですか?
事業承継の種類によって期間は異なります。親族内承継の場合、後継者の育成から権限移譲まで含めると5〜10年かかるケースもあります。従業員承継では、候補者選定から権利移転まで通常3〜5年程度が目安です。M&Aによる事業承継の場合、本格的な準備開始から完了までの実務的なプロセスは半年〜2年程度が一般的です。ただし、M&Aであっても買い手との相性や条件面での調整に時間を要することもあるため、余裕を持ったスケジュール設定が望ましいでしょう。
個人事業主の税理士事務所でも事業承継・M&Aは可能ですか?
はい、個人事業主の税理士事務所でも事業承継・M&Aは可能です。ただし、法人とは異なり事業譲渡の形となります。個人事業の場合、のれん代や顧客資産の評価、個別資産の移転手続きなど、法人とは異なる考慮点があります。また、個人事業主の場合は承継前に法人成りを検討することも一つの選択肢です。法人化によって譲渡手続きが簡素化されるとともに、税務面でのメリットが得られる可能性もあります。M&A相談センターでは、個人事業主の方の事業承継についても豊富な実績がありますので、お気軽にご相談ください。
- M&A相談センター
- M&Aガイドブック
- 譲渡への第一歩はここから
- 会計事務所・税理士事務所の事業承継の流れや成功させるためのポイントを解説
カテゴリから探す
人気記事ランキング
おすすめページ
M&A相談センターについて