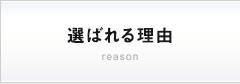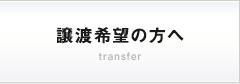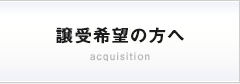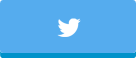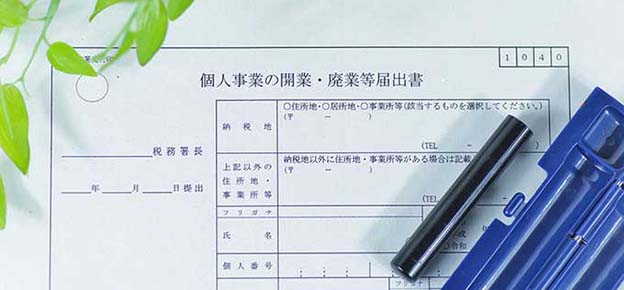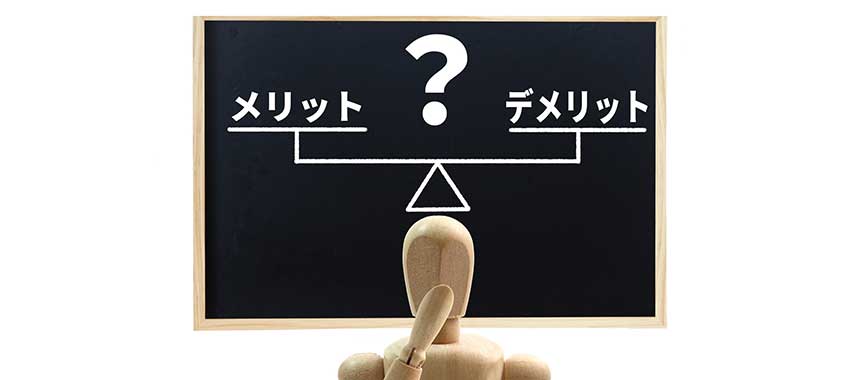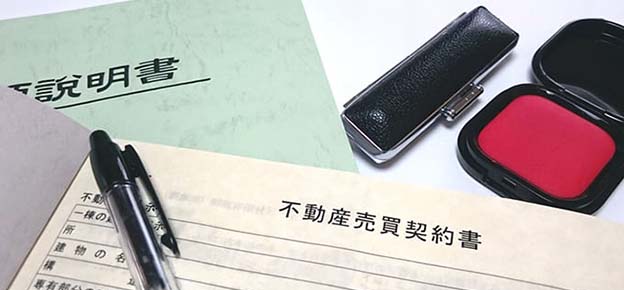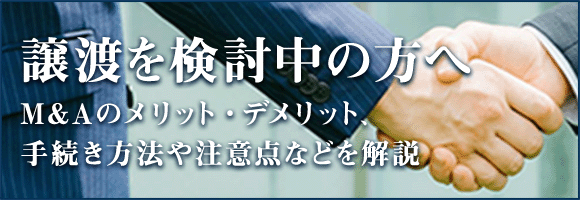後継者がいない会計事務所は廃業なのか?残された選択肢と対策を解説
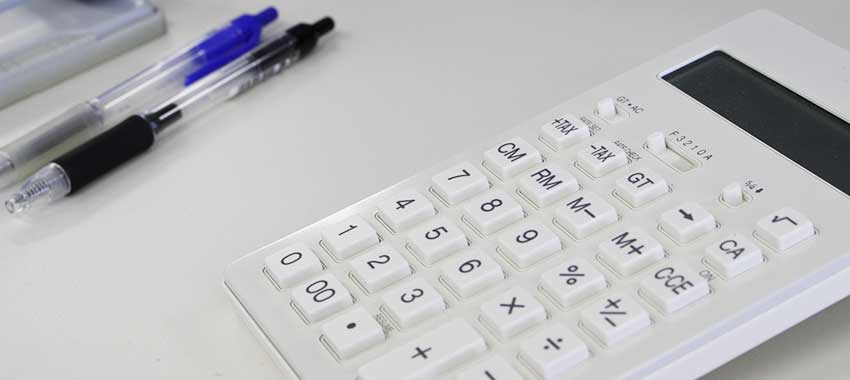
更新日:
では、後継者がいなければ廃業しなければならないのでしょうか。ここでは、後継者がいない場合の選択肢と対策について解説します。

- この記事の監修者
- イデア総研税理士法人 福岡支店
代表社員 南 彰悟
会計事務所を取り巻く環境
現在、個人経営の会計事務所や小規模税理士法人は厳しい環境に置かれています。特に大きな問題として「所長の高齢化と後継者問題」「顧客獲得などの競争の激化」が挙げられます。それぞれについて見ていきましょう。
所長の高齢化と後継者問題
今、多くの企業で問題となっているのが、経営者の高齢化と後継者不足です。会計事務所であっても、一般の企業と同じように、経営者の高齢化と後継者不足が問題となっています。
日本税理士会連合会が平成26年に行った「第6回税理士実態調査」では、税理士の年代別の構成割合が公表されています。それによると、税理士の年齢でもっとも多い割合を占めていたのが60歳代で、全体の30.1%でした。次に多かったのが50歳代で全体の17.8%、40歳代の17.1%、70歳代の13.3%と続きます。80歳代も全体の10.4%と多く、60歳以上が占める割合は、全体の半数を超える53.8%となっています。
対して若い世代の税理士を見ていくと、20歳代では0.6%、30歳代では10.3%と合計でも10%強しかいないことがわかります。「第6回税理士実態調査」からも、会計事務所の所長の高齢化と後継者不足が、税理士業界全体の課題として浮き彫りになっているのがわかります。
顧客獲得などの競争の激化
インターネットの普及などにより、税理士の仕事は昔に比べてシステマティックになってきています。そのため、税理士や職員、顧客の多い大手の税理士事務所が増えてきました。一方で、税理士が個人で仕事を行っている会計事務所も多くあります。
また、税理士の報酬には一定の目安はありますが、今は自由に事務所の裁量で決めることが可能です。そのため、顧客の獲得や事務所を大きくするために、あえて低い金額で仕事を請け負う税理士がいたり、報酬の高い仕事を大手税理士事務所が引き受けたりなど、個人税理士が経営している会計事務所は顧客獲得の競争で苦しんでいる現状があります。
これらの理由から廃業に陥る会計事務所も増加しています。そうならないためにも、選択肢として、M&Aによる事業の存続を考えている会計事務所も増えています。
後継者がいない場合の選択肢とは?
では、子どもや親族の中に後継者がいない場合、どのような選択肢が考え得るのでしょうか。以下の4パターンについて解説します。
- 廃業
- 事務所の従業員に承継
- 外部から後継者を招く
- M&Aによって第三者へ譲渡する
廃業する場合の対応とは
「子どもなど、親族に引き継ぐ人がいないため廃業する」と決めている場合、まずは顧問先の引き継ぎ先と、従業員の就職先を探します。顧問先を引き継いでくれる税理士を探すには時間がかかるので、廃業に向けての準備期間を数年見ておく必要がありますが、自分のペースで廃業までの準備を進められます。
顧問先や従業員の引き継ぎ先が決まれば、資産の売却や負債・借入金などの返済、廃業届の届け出など廃業の手続きを行います。
資産を売却し、負債を返済しても負債が残ってしまう場合、個人経営の事務所の場合は所長が個人財産から返済しなければなりません。
事務所の従業員に承継する
事務所に税理士資格を持つ人がいれば、従業員に事業承継するのも有効な手段です。事務所の方針などを理解している従業員が事業承継してくれれば、所長税理士としても安心できます。
ただし、事務所の経営には税理士業務と異なる資質が必要になります。有資格者の従業員を後継者として育て、事業承継を行うには時間をかけて進めなければなりません。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 何よりも、従業員本人が後継者になることを承認してくれなければ話が始まりません。無理やり押し付けて、事務所を辞められては意味がないので、慎重に進めましょう。

- イデア総研税理士法人 福岡支店代表社員 南 彰悟
外部から後継者を招く
「親族や事務所内に後継者はいないが、知り合いに駆け出しの税理士がいる」といった場合、事務所への招聘を検討してもよいでしょう。
ただし、事務所の従業員と外部からの後継者がうまくコミュニケーションできないと、どちらかが辞めてしまうこともあります。所長が両者の間に立ち、うまく引き継ぎできるかがカギです。
M&Aで第三者へ譲渡する
実は「親族、社内、社外のいずれも後継者が見当たらないとなれば、廃業しかない」というわけではありません。M&Aで第三者へ事務所を譲渡するという選択肢があります。一般的なM&Aには株式譲渡や事業譲渡、合併などいくつかの方法がありますが、個人経営の会計事務所を譲渡する場合、事業譲渡というかたちを選択することが多いです。
スムーズにM&Aをするための事前準備
M&Aに向けての事前準備で重要な点として、以下の2点が挙げられます。
- 日々の業務とM&Aを並行して進められるよう、M&Aの流れを把握して計画を立てる
- できるだけ高い価格で事務所を売却できるよう、事務所の価値を上げる
これらのポイントを踏まえ、具体的にどのような準備をすればよいか見てみましょう。
廃業のスケジュール作成
引退・廃業の目標日を設定し、廃業までのスケジュールを立てましょう。スケジュールには、以下のような項目を盛り込む必要があります。
- 情報収集
- M&Aをサポートしてくれる会社や機関(金融機関や商工会議所など)を探し、契約を結ぶ
- M&A…譲渡先の選定、交渉、買収監査(デューデリジェンス)、契約成立・決済
- PMI(M&A成立後の経営・業務統合)
M&Aをサポートしてくれる企業・機関と契約譲渡先を探して交渉し、M&Aを成立させるまで少なくとも半年、長ければ数年かかります。また、PMIの局面では、所長が譲渡先事務所に数か月から数年間在籍するケースが多いです。
事務所の資産や負債の整理
準備段階で事務所の資産や負債の状況を把握し、可能な場合はM&Aの交渉までに負債を減らしましょう。財務状況は譲渡先によるデューデリジェンスでも徹底的に調べられ、事務所の価値にも影響を与えます。
スタッフや従業員の対応策
M&Aに向けての準備段階で、スタッフや従業員に対する対応策としては「スキルを磨いてもらうこと」が挙げられます。デューデリジェンスでは、スタッフや従業員の業務経験や資格取得状況も対象になるからです。
なお、スタッフや従業員にM&Aの件を伝えるのは、クロージング後です。準備段階では、従業員に対して譲渡先の情報やM&A後の待遇について誠意をもって説明する心づもりをするとともに、M&Aの交渉で自事務所の待遇が低くならないように条件を整理しておきましょう。
会計事務所のM&Aのメリット
会計事務所でM&Aが増加している背景に、譲渡会計事務所(売り手)と譲受会計事務所(買い手)の双方に多くのメリットがあることが挙げられます。
そこで、ここでは譲渡会計事務所と譲受会計事務所のそれぞれのメリットを見ていきましょう。
譲渡会計事務所のメリット
譲渡会計事務所のメリットには、次のようなものがあります。
・後継者問題の解消
税理士業界では後継者が不足しており、後継者がいないため廃業の危機に陥っている会計事務所が多くあります。会計事務所のM&Aでは、大手会計事務所や若い税理士のいる会計事務所に事業を引き継ぐことで、後継者問題の解消になります。
・従業員の雇用の継続と顧問先の保護
会計事務所が廃業してしまうと、困るのが会計事務所で働いている従業員と会計事務所に会計業務を依頼している顧問先です。従業員は、会計事務所が廃業すると働き先がなくなり、たとまち収入が途絶えて生活が苦しくなります。顧問先も新しい会計事務所を見つけて、一から自社の状況や仕事の流れなどを説明する手間が増加します。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 会計事務所のM&Aでは、原則、従業員や顧問先を引き継ぐことを考えます。そのため、従業員の雇用の継続ができたり、顧問先も新たな会計事務所を探す手間がなくなったりなど、会計事務所の廃業からおこるさまざまな問題を減らすことができます。

- イデア総研税理士法人 福岡支店代表社員 南 彰悟
・所長の仕事の継続
会計事務所のM&Aの場合、契約内容によっては譲渡会計事務所の所長が譲受会計事務所で仕事を続けることもできます。仕事の継続ができるため、所長自身が仕事を無くす心配もなくなります。
・引退後の資金の獲得
実は、譲渡会計事務所の所長が引退した後の資金獲得も、会計事務所のM&Aのメリットのひとつです。会計事務所のM&Aは、会計事務所とその事業を売却することになるので、まとまった資金を手に入れることができます。そのため、所長の年齢などによっては、そのまま引退しても、老後の資金に困らずに生活することが可能となります。
譲受会計事務所のメリット
譲受会計事務所のメリットには、次のようなものがあります。
・顧客の確保による事務所の成長
会計事務所のM&Aによる譲受会計事務所のメリットのひとつが、事務所の成長です。会計事務所のM&Aでは、譲渡会計事務所の顧客を引き受けることができます。顧問先が増加すれば、それだけ事務所の収益が増え、経営が安定します。
また、顧問先から新たな顧問先の紹介を受けるなど、会計事務所のさらなる成長機会を得ることができる可能性も広がります。
・優秀な人材の確保
優秀な人材を確保できることも、会計事務所のM&Aのメリットです。税理士業界では高齢化が進み、若い税理士が不足している状況であったり、急激に進んでいる会計業務のIT化への対応が求められていたりする状況です。そのため、どの会計事務所でも、優秀な人材の獲得を今まで以上に望んでいる状況です。会計事務所のM&Aでは、人材も引き継ぐことが可能なため、譲渡会計事務所の優秀な人材も確保できます。
・新しい地域での新規開拓
会計事務所では、一定の地域だけでなく、全国規模で顧客を抱える事務所も増えてきています。会計事務所のM&Aでは、新しい地域での新規開拓の足掛かりとなります。これまでに顧客がいなかった地域の会計事務所をM&Aをすることで、その地域での新規開拓がしやすくなるメリットを得ることが可能です。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - これまでに顧客がいなかった地域の会計事務所をM&Aすることで、その地域での新規開拓がしやすくなるメリットを得ることが可能です。

- イデア総研税理士法人 福岡支店代表社員 南 彰悟
会計事務所のM&Aの注意点
ここまでは、会計事務所のM&Aにおけるメリットを見てきました。しかし、会計事務所のM&Aでは、注意しないといけない点もいくつかあります。代表的なものに、次のような注意点があります。
・人材流出のリスク
会計事務所のM&Aでは、譲渡会計事務所から譲受会計事務所に人材を引き継ぐことができます。しかし、必ず引き継げるということではありません。従業員の待遇が異なったり、譲受会計事務所の雰囲気に合わなかったりして、譲受会計事務所に移籍しない従業員がでてくる可能性もあります。
譲渡会計事務所では、従業員の雇用が守り切れないことがデメリットとなり、譲受会計事務所では、M&Aにより仕事量が増えた結果、それを賄える人材の不足に陥る危険性があります。会計事務所のM&Aをする前には、譲渡会計事務所と譲受会計事務所の間で従業員の待遇などをしっかりと話し合いしておく必要があります。
・顧問先の解約リスク
会計事務所のM&Aで人材流出のリスクとともにあるのが、顧問先の解約リスクです。
顧問先が新しい会計事務所との顧問契約を嫌がり、解約する可能性もあります。顧問先の解約リスクを防ぐためには、顧問先に何度も説明をするなど、M&Aをする前にしっかりとした手回しをしておく必要があります。
事務所廃業後の人生設計と次のステップ
M&Aによって事務所を譲渡先に無事に引き渡し終えた所長税理士は、新たな人生を歩むことになります。M&Aを考え始めると同時に、廃業後の計画も立てておきましょう。
廃業後の人生設計
廃業時の年齢にもよりますが、70歳で廃業すると10数年の“次の人生”が続く可能性があります。M&Aを考えるとき、廃業後の生活についても考えておく必要があります。廃業後の生き方については、以下のようなパターンが想定できます。
- 事務所(事業)を譲渡して得た利益で、悠々自適の生活を送る。
- 事業譲渡で利益を得るのに加え、譲渡先に顧問として籍を置いて相談などに応じ、一定の報酬を得る。
- 事業譲渡で得た利益を元手に別の事業を興す。
いずれの道を進むにせよ、第二の人生の見通しを立てることで、事務所の売却希望価格や、希望価格を得るために準備期間で何をすればよいかが見えてくるでしょう。
別事業の開始やコンサルタントとしての活躍
事業譲渡益を元手に、不動産賃貸業や飲食業など税理士事務所とはまったく異なる事業を始める人がいます。業種は異なっても、経営を行ううえで会計・税務の知識を役立てられるのは元・税理士の強みです。
また、自ら税務書類の作成や税務の代理といった業務に関わることはなくなっても、経験を活かして中小企業を支援するコンサルタントとして活動するという道もあります。
記事監修者 南税理士からのワンポイントアドバイス
税理士も他業種と同様、高齢化が進み、後継者問題が近年の課題です。有資格者であることが後継者の条件となっているため、事業承継が思うように進まない事情から、廃業を考える所長税理士の方は少なくありません。
親族内・社内承継、または後継者の外部招聘が難しい場合、M&Aによる第三者への譲渡という選択肢があります。M&Aには、従業員の雇用を確保できたり、所長税理士が譲渡対価を得たりして、廃業よりも多額の資金を手元に残せたりするメリットがあります。
廃業をお考えの方は、ぜひM&Aも選択肢として検討してみてください。

- この記事の監修者
- イデア総研税理士法人 福岡支店
代表社員 南 彰悟(公認会計士・税理士)
カテゴリから探す
人気記事ランキング
おすすめページ
M&A相談センターについて