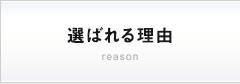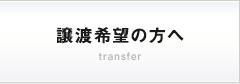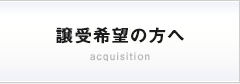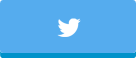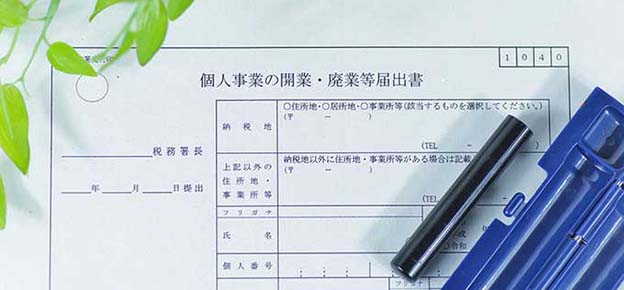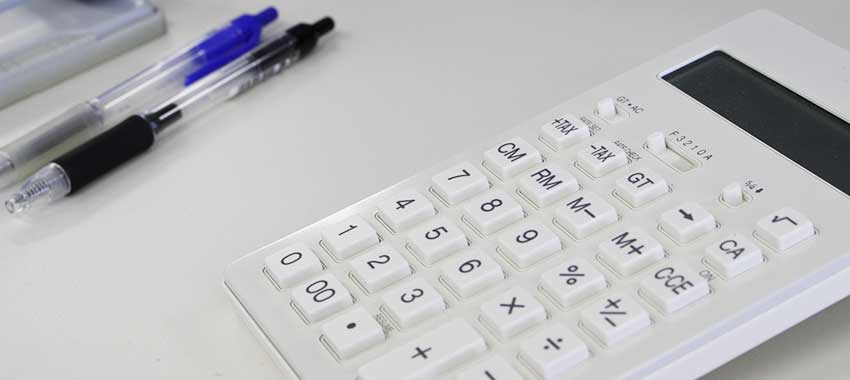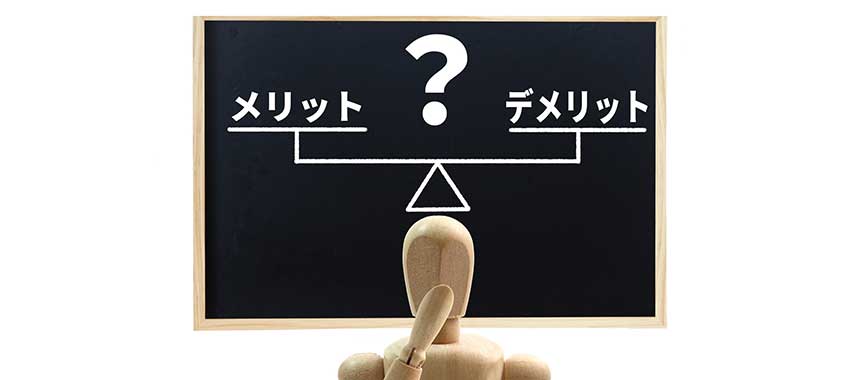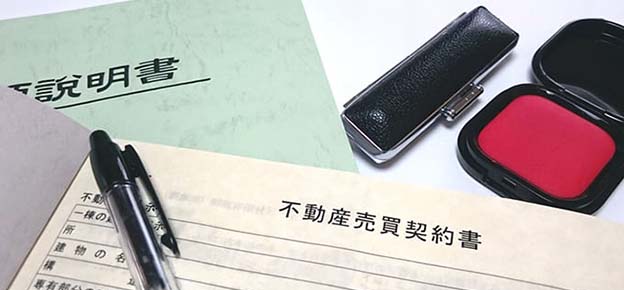税理士事務所・会計事務所の現状や売却の流れ・相場を解説

更新日:
健康上の理由などから、経営する税理士事務所・会計事務所を売却し、従業員の雇用を売却先に委ねたいと考えている税理士の方は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、税理士事務所・会計事務所を取り巻く環境や売却の流れ、売却相場について解説します。

- この記事の監修者
- アセンディア税理士法人
代表 中釜 和寿(公認会計士・税理士)
税理士事務所・会計事務所の現状
報酬の減少や後継者問題など、税理士事務所・会計事務所を取り巻く現状はシビアです。まずは税理士事務所・会計事務所の現状について詳しく見てみましょう。
税理士事務所・会計事務所の8割以上は個人経営
総務省と経済産業省が5年ごとに実施している「令和3年 経済センサス‐活動調査」によると、令和3年における全国の税理士事務所・会計事務所の数は3万2,246か所となっています。このうち、個人経営の事業所は83.2%、税理士法人など個人経営以外の形態をとっている事業所は16.8%となっており、税理士事務所・会計事務所の多くが小規模の個人事務所であることがわかります。
小規模の個人事務所の割合が圧倒的に多い税理士事務所・会計事務所ですが、個人と税理士法人などで売上高を比較すると個人52.3%、個人以外47.7%となっており、ほぼ互角です。これは、税理士法人などが事業規模の大きい顧問先を相手にしていることが背景にあると考えられます。
さらに、現在はクラウド会計ソフトの普及により、中小企業や個人事業主は税理士を頼らなくても基本的な税務・会計処理業務を行えるようになっています。このため、小規模税理士事務所・会計事務所が顧問先から得られる報酬は、以前よりも減少しています。
税理士の5割以上は60代以上、若手合格者は減少
また、日本のあらゆる産業において、少子高齢化による後継者不足が大きな問題になっていますが、税理士事務所・会計事務所においても例外ではありません。日本税理士会連合会が平成26年に実施した実態調査によると、税理士の年齢層ごとの割合は以下のようになっており、60代以上が53.8%を占めています。
| 20代 |
0.6%(187人) |
|---|---|
| 30代 |
10.3%(3,358人) |
| 40代 |
17.1%(5,599人) |
| 50代 |
17.8%(5,817人) |
| 60代 |
30.1%(9,868人) |
| 70代 |
13.3%(4,343人) |
| 80代 |
10.4%(3,421人) |
60代以上の税理士が経営する税理士事務所・会計事務所では、事務所を引き継いでくれる若い税理士を確保することが課題となりますが、若手税理士が減少しているため、採用は簡単ではありません。
|
|
25歳以下 |
26~30歳 |
31~35歳 |
36~40歳 |
41歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
|
平成27年度 |
59人 |
146人 |
172人 |
199人 |
259人[011] |
|
平成28年度 |
53人 |
123人 |
151人 |
150人 |
279人[012] |
|
平成29年度 |
58人 |
124人 |
163人 |
173人 |
277人[013] |
|
平成30年度 |
51人 |
99人 |
133人 |
142人 |
247人[014] |
|
令和元年度 |
63人 |
112人 |
158人 |
148人 |
268人[015] |
|
令和2年度 |
43人 |
96人 |
126人 |
136人 |
247人[016] |
|
令和3年度 |
41人 |
74人 |
98人 |
116人 |
256人[017] |
表は過去7回の税理士試験における5科目到達者の数を年齢層別に示したものです。5科目合格の到達までに時間がかかる事情はあるものの、26~30歳・31~35歳・36~40歳の層で、合格者が大きく減少しています。
大手税理士法人に比べ、給与や待遇面でハンデがある個人経営の事務所などは、この層の採用が難しくなっています。さらに、新型コロナ禍の影響で、廃業に追い込まれる中小企業も増え、一部の大手税理士法人を除いて多数の税理士事務所・会計事務所を取り巻く環境は一層厳しいものになっていると考えられます。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - テクノロジーの進歩や人口減少などマクロ環境の変化に伴い、今後は税理士業界でも経営統合や小規模事務所の淘汰が進む可能性は否めません。日々の業務だけでなく、中長期的な視点から環境変化が事務所の経営に与える影響を考えてみても良いかもしれません。

- アセンディア税理士法人代表 中釜 和寿
税理士事務所・会計事務所の売却のメリットとデメリット
個人経営の税理士事務所・会計事務所では、生き残りをかけて事務所を税理士法人などに売却するケースがあります。
では、事務所を売却するメリットとデメリットについて見てみましょう。
税理士事務所・会計事務所の売却のメリット
【売り手】後継者問題の解決
事務所を売却する側のメリットとして、後継者問題を解決できることが挙げられます。
中小規模の事務所を経営する70代、80代の所長税理士にとって、後を継いでくれる人材の確保は簡単ではありません。一般的に税理士や公認会計士が事務所のトップになるため、親族内に税理士や公認会計士がいないと、親族内承継が難しくなります。
また、外部から人材を確保するのも簡単ではありません。税理士資格を持っている若手・中堅年齢層の人材は減少しており、給与・待遇面で有利な大手税理士法人に流れる傾向にあるからです。
そのような状況で事務所をより大きな税理士法人などに売却すれば、買い手側に自身が育ててきた事務所を託すことができます。
【売り手】職員の雇用
売り手側のもう一つのメリットとして、職員の雇用継続が挙げられます。
事務所内に数人の職員はいるが、税理士資格を持っている者が誰もおらず、所内に後継者を求められないといったケースは少なくありません。この場合、所長がリタイアしてしまうと、職員は路頭に迷ってしまいます。
所長がリタイア前に事務所を売却することで、経営者は変わるものの、職員は引き続き仕事を続けられます。売り手である所長は売却時に、自事務所の職員の待遇について買い手と十分に話し合い、売却先で自事務所の職員が良い環境・待遇で働けるように交渉しましょう。
【売り手】顧問先の不安解消
売り手側の3つ目のメリットとして、顧問先の不安解消につながることが挙げられます。
高齢の所長税理士と顧問契約を結んでいる企業や個人は、顧問税理士がリタイアすると誰に税務面の相談や依頼をすればよいか不安になるものです。所長がみずから交渉し、託した買い手の税理士に業務が引き継がれることで、顧問先の不安を解消できます。
【買い手】新たな顧客と従業員の獲得
税理士事務所・会計事務所を買収する側のメリットとして、新たな顧客や従業員の獲得が挙げられます。
通常、新規顧客を獲得するには、役所などで開催される税務相談や、中小企業者・自営業者などが集まるイベントなどに参加したり、ネット上でプロモーション活動を展開したりと、手間と費用がかかります。しかし、事務所を買収すると、まとまった数の新規顧客が得られます。
また、人材を採用し、教育するにも時間がかかります。事務所を買収することで、複数の経験豊富なスタッフを迎え入れられます。
新たな顧客と従業員をまとめて獲得できることは、業容拡大に大きく寄与します。
税理士事務所・会計事務所の売却のデメリット
税理士事務所・会計事務所の売却には、デメリットもあります。売却する側のデメリットとともに、売却された事務所を買収した側のリスクについても解説します。
【売り手】売却に対する課税
所長税理士が経営する税理士事務所・会計事務所を売却するデメリットとしては、売却益に対して税金がかかることが挙げられます。
事務所が個人経営なら譲渡所得税、法人なら法人税が売却益に対して課税されます。また、事務所の売却にかかわって事務所の資産を譲渡すると、消費税が課されます。
【買い手】買収した事務所の従業員・顧問先が離れるリスク
買い手にとっては、買収した事務所の従業員や顧問先が、買収後に離れるというリスクがあります。
「前事務所よりも待遇が悪くなった」「新事務所の経営方針についていけない」と従業員が感じると、退職してしまうことがあります。また、売り手側から引き継いだ顧問先に「前の税理士先生よりも対応が悪くなった」などの印象を持たれてしまうと、やはり顧問契約解除につながる可能性があります。
買い手側は、買収した事務所の従業員や顧問先が離れないよう、買収後しばらくは、売り手である所長に在籍してもらい、前事務所の従業員や顧問先を買い手側に引き継いでもらうとよいでしょう。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 税理士事務所にとっても事業承継は中長期な視点で解決すべき大きな経営課題です。事務所を代表する税理士のみでなく、事務所の職員や長期に渡り税務顧問を担当してきたクライアントなどすべてのステークホルダーにとって最適な選択肢が採れるよう、様々な可能性を考えながら長期間にわたって計画・準備を進めることが重要となります。

- アセンディア税理士法人代表 中釜 和寿
税理士事務所・会計事務所の売却の流れと価格相場
ここでは、税理士事務所・会計事務所を売却する流れや、売却価格の相場について解説します。
税理士事務所・会計事務所の売却の流れ
(1)事前準備
事務所を売却する理由や、売却先の条件などをまとめておきます。
(2)仲介業者選定
事務所の売却先を探し、売却価格や条件などを交渉するにあたり、仲介を手掛ける専門家の手を借ります。仲介業者には、銀行や M&A仲介会社などがあります。
(3)交渉
売却先の条件を仲介業者に伝え、候補者を複数ピックアップしてもらいます。候補の中から選んだ相手と秘密保持契約を結び、お互いの詳細情報を開示して交渉を開始します。
事務所の従業員にとっては、売却先が新たな職場となります。売却金額などの条件に加え、相手の経営理念や今後の事業展開など、従業員が安心して働ける環境かどうかも確認し、売却先としてふさわしいかを判断しましょう。
(5)デューデリジェンス
デューデリジェンスとは、買い手が売り手の帳簿などを査定し、売り手が提示している売却価格や契約内容などが妥当であるか判断するものです。
(6)価格交渉・支払い
デューデリジェンスを踏まえ、必要に応じて売り手・買い手の間で価格交渉が行われます。買収の条件を細かいところまで詰め、最終譲渡契約書を取り交わします。売り手は買い手から売却代金を受け取ります。
(7)クロージング
「クロージング」とは、経営権移転の手続きのことです。買収の方法には株式譲渡や事業譲渡、合併などいくつかありますが、経営権移転の具体的な手続きは買収方法によって異なります。
たとえば、事業譲渡であれば、第三者による承認を得ながら資産や負債の移転、従業員雇用の引継ぎなどを進めます。
(8)PMI
「PMI」とは「ポスト・マージャー・インテグレーション(Post Merger Integration)=買収後の統合プロセス」のことです。買い手が、買収した事務所の資産や社員、顧客などを自身の組織になじませるために行う統合作業を指します。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 事業承継を考える税理士事務所にとって、M&Aは何度も繰り返し経験する性質のものではなく、一度切りのトランザクションとなることが多いです。ディールを実行する中で、予期せぬリスクが顕在化し「あの時こうすれば良かった」となることを避けるため、その計画と実行にあたっては経験ある専門家の利用をお勧めします。

- アセンディア税理士法人代表 中釜 和寿
税理士事務所・会計事務所の売却の価格相場
事務所の売却交渉を行うにあたり、相場を知っておくことが重要です。相場とはかけ離れた高額を提示して交渉が進まなかったり、デューデリジェンスの結果、買い手から相場以上の売却価格の値下げを要求されたりする事態を防げるからです。
税理士事務所・会計事務所の売却は、1年間の顧問報酬または2~3年分の営業利益を基準に売り手・買い手で交渉が行われることが多いです。売却価格の決定には、事務所の立地や売却の事情なども加味されます。
まとめ
事務所の売却を成功させるには、売却までの手順や相場を知り、あらかじめ売却条件を細部まで詰めておくことが重要です。さらに、買い手へ売却後、従業員や顧問先の離脱を防ぐために、準備段階で彼らに事情を十分説明したり、買い手候補と自事務所との相性をチェックしたりする必要もあります。売却の準備を進めるには、業界に精通した仲介会社に依頼することをおすすめします。
記事監修者 中釜税理士からのワンポイントアドバイス
今後、私たちの業界においても大きな業界再編やテクノロジーを活用したサービスの転換が起こる可能性は高いと考えます。私たちを信頼して税務顧問を任せてくださったクライアントや、ともに働くことを選んでくれた税理士事務所の職員を守るため、長期に渡って最適な事業承継の在り方ついて検討をすることが必要です。
また、M&Aの実行にあたっては買い手・売り手双方が短い期間で重要なリスクに対応することが求められます。事前準備から買収後統合のフェーズまで、経験ある専門家の力を借りながら皆が納得できる形でM&Aを進めてゆくことが重要です。

- この記事の監修者
- アセンディア税理士法人
代表 中釜 和寿(公認会計士・税理士)
カテゴリから探す
人気記事ランキング
M&A相談センターについて