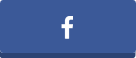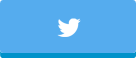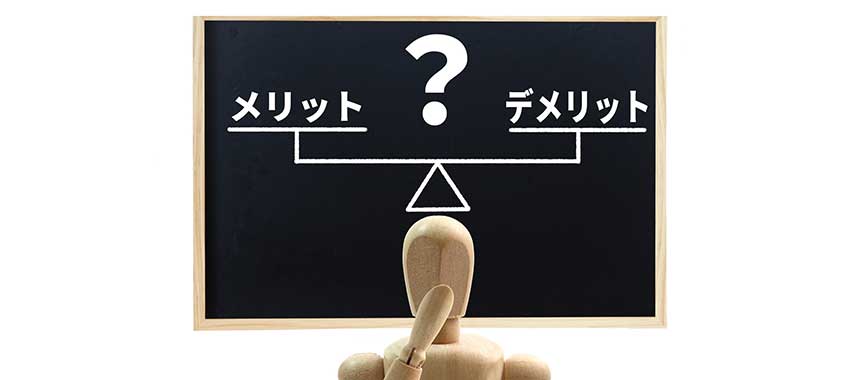経営者が認知症になったら 事業承継への影響と対応方法解説
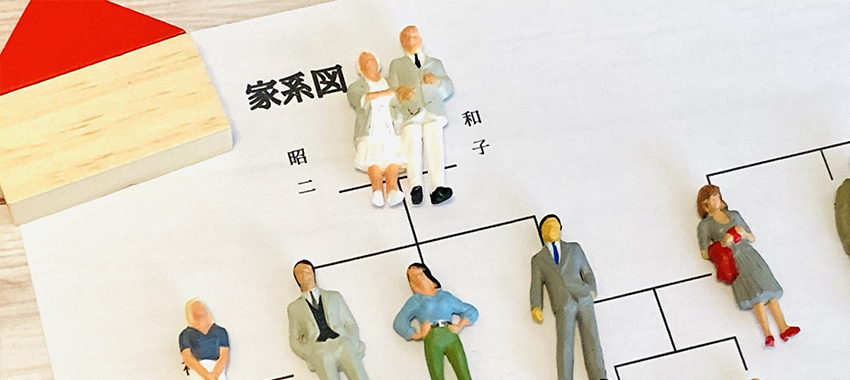
更新日:
しかし、成年後見人を立てるとM&Aによる事業承継が可能です。ここでは、成年後見制度や成年後見人を通じてのM&Aについて解説します。
経営者が認知症になると企業経営に大きな影響を及ぼす
少子高齢化に伴い、中小企業の経営者の高齢化も進んでいます。年を重ねるにつれて、認知症のリスクが高くなります。認知症になれば、重要な経営判断ができなくなる場面が増えるでしょう。
高齢化が進む経営者の認知症リスク
帝国データバンクが2021年に行った調査によると、全国の経営者のうちで60代以上が占める割合は47.1%となっています。そのうち、70代以上が占める割合は20.2%に上っており、経営者のおよそ4人に1人は70代以上ということになります。
年を重ねると気になるのが認知症のリスクです。65歳以上になると認知症になるリスクが高まるとされ、厚生労働省が2014年にまとめた推計では、2025年には65歳以上の認知症患者が最大で約730万人にのぼると考えられています。
経営者が認知症になると法律行為が無効になる
経営者が認知症になると、契約や権利行使などの「法律行為」が無効になります。
法律行為が有効になるには、自分の行動の動機と結果を判断できる「意思能力」を持っていることが前提とされているからです。認知症患者は「なぜその行動を行うのか」「その行動の結果どうなるのか」といったことを自身で判断できなくなるため、意思能力を持っていないとみなされてしまいます。
例えば、株式の売買や贈与、融資の契約、株主総会における決議などが無効とされてます。事業承継には、さまざまな法律行為を伴います。高齢化で事業承継を進めようと考えていた場合、経営者が認知症になってしまうと、自身の判断で事業承継ができなくなるリスクがあるのです。
経営者が認知症になった場合の事業承継
経営者が認知症になってしまった場合、成年後見制度を活用してM&Aによる事業承継を進める方法があります。
成年後見人等が代理で法律行為を行う
成年後見制度とは、認知症などが原因で法律行為ができない人を法的に支援する制度です。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度に分かれています。認知症になってしまった経営者の法律行為に関わってくる制度は、法定後見制度です。
・任意後見制度
認知症などになる前に、本人自身が「任意後見人」を選び、自分の代わりにしてほしいことを任意後見契約によって決めておく制度です。
・法定後見制度
すでに認知症などになってしまった場合、その程度に合わせて「成年後見人等」が代理で法律行為を行ったり、本人が法律行為を行う際に同意を与えたり、後からの取り消しを行ったりできます。
「成年後見人等」は、支援が必要となる程度によって以下のように3タイプに分かれています。いずれも本人、または配偶者、四親等内の親族などが申立てをし、家庭裁判所が選任します。
| 成年後見人等のタイプ | 判断能力の程度 | 成年後見人等ができること |
| 補助人 | 不十分 | 申立てにによって裁判所が定めた行為について、代理・同意または取り消しができる |
| 保佐人 | 著しく不十分 | ・相続の承認、放棄、訴訟など民法13条1項記載の行為や、申立てによって裁判所が定めた行為について、同意または取り消しができる ・申立てにより裁判所が定めた行為について代理で行える |
| 成年後見人 | 全くない | 原則すべての法律行為について代理で行ったり同意、取り消しができたりする |
成年後見人等を通じてM&Aを行う
経営者が重度の認知症になった場合、経営上必要な契約や経営判断などができなくなります。そのような場合、家庭裁判所は親族などからの申立てによって、成年後見人等を選任します。上述したように、判断能力が全くない場合は「成年後見人」が選ばれます。
成年後見人等を選任するには、以下のようなステップを踏む必要があります。
申立人を決め、必要書類を本人(この場合は経営者)の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する。この際、成年後見人等の候補者を立てる。
調査官が本人や親族などと面談を行い、本人の判断能力を確認する。
家庭裁判所が成年後見人等を選出する。
申立ての際には、親族や弁護士などを成年後見人等の候補者として立てますが、第三者である弁護士などが選出されることが多いです。親族を成年後見人等に選出することで、成年後見人等の中立性が維持できないケースが少なくないからです。なお、代表取締役である経営者に成年後見人等が選任されると、経営者は取締役としての資格を失います。
親族の中に会社を引き継ぐ人がいない場合、成年後見人等が会社を経営することは事実上困難です。そのような場合、M&Aで株式や事業を譲渡することで、第三者の企業に事業承継を行う方法が有効です。
成年後見人等は経営者の状況に応じて行使できる権利が異なりますが、成年後見人の場合は財産に関するすべての法律行為について代理権を行使できます。
M&Aでは、取引を行うなかでさまざまな契約書や合意書などに署名を行う必要があります。また、経営者が所有する株式を譲渡しなければなりません。このような場合、成年後見人等が経営者の代理として法律行為をします。M&Aで得た売却益は、もちろん経営者に支払われます。
成年後見人等の課題と対策
経営者が認知症になった際、成年後見人等の支援を得ながら事業承継を進めることは可能です。しかし、成年後見人等を選ぶ法定後見制度には課題があります。
・成年後見人等の選出までに時間がかかる
成年後見人等の申立てから家庭裁判所による選出までには、早くて1、2か月が必要とされています。本人の判断の能力や事案の内容によっては、審理期間が長びくこともあるため、それ以上かかることもあります。
申立ての際には医師の診断書や戸籍・住民票、不動産の登記事項証明書や有価証券の証明書などを提出しなければなりません。そのため必要書類を集めるための時間も必要です。
・家庭裁判所が選出する成年後見人等の妥当性
成年後見人等を選出するのは家庭裁判所です。成年後見人等を選ぶ基準は、本人の身を守り、財産管理を適正に行ってくれる人」です。つまり経営者に代わって経営判断ができる人が選ばれるわけではありません。
上述したように、成年後見人等に選ばれた親族が不正を働くことを防止するため、成年後見人等は親族よりも弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる傾向にあります。
このように、さまざまな課題がある法的後見制度ですが、近年変化の兆しがあります。法的後見制度の利用が低迷するなか、国は制度の利用を促進するため、2017年に成年後見人等の選出方法の見直しを行いました。2019年には最高裁判所が「成年後見人等にふさわしい親族などがいる場合、親族を選出することが望ましい」との見解を示しています。今後は成年後見人等の選出に変化が起きる可能性があります。
また、成年後見制度には、法的後見制度と並んで任意後見制度があります。任意後見制度は、本人が元気なうちに任意後見人と契約を結んでおく制度です。後継者がいる場合、あらかじめ後継者を任意後見人にしておくのも一つの方法です。
まとめ
コロナ禍で人々の活動が普段よりも低下する中、高齢者の間で認知症が進行しているケースは増加しています。経営者が認知症になってしまうと、契約や財産の譲渡といった法律行為が無効になります。このような状態では、さまざまな経営判断ができなくなります。事業承継を行おうとしても、そこに付随する法律行為は一切できません。
なお、民法の改正により、18歳以上の法律行為が有効になったため、事業承継の幅は広がりました。
認知症のため、経営者がさまざまな経営判断を下せなくなった場合法定後見制度を利用して成年後見人等を立て、代理で事業承継を進めてもらう方法があります。親族などに後継者がいない場合は、M&Aで第三者に事業承継ができます。ただし、法定後見制度は法律に関する専門的な知識が必要です。制度の活用を検討する場合は弁護士などに相談しましょう。
カテゴリから探す
人気記事ランキング
M&A相談センターについて