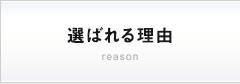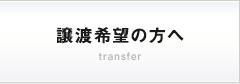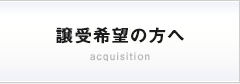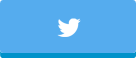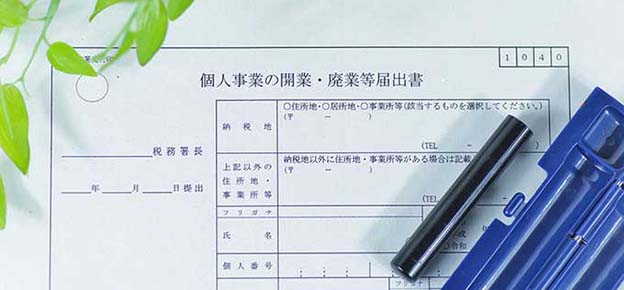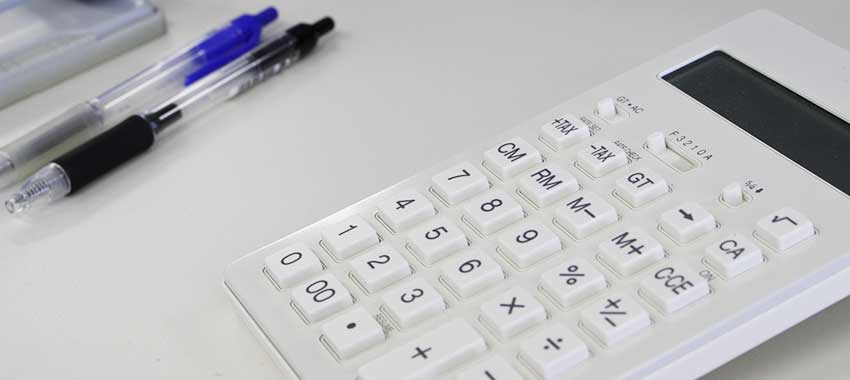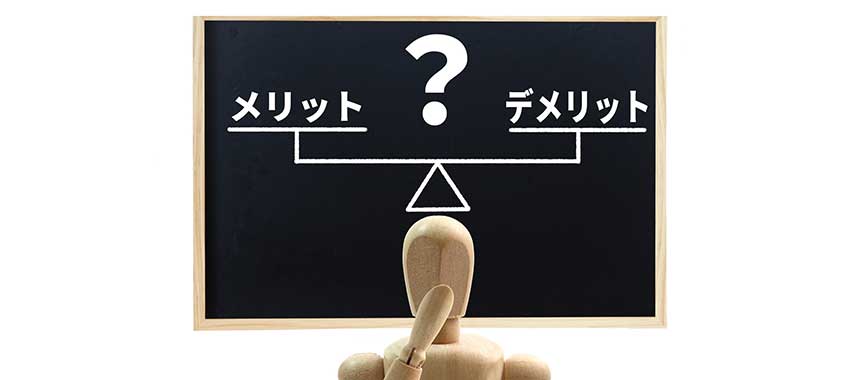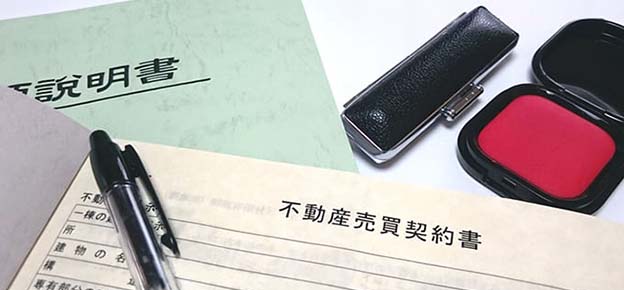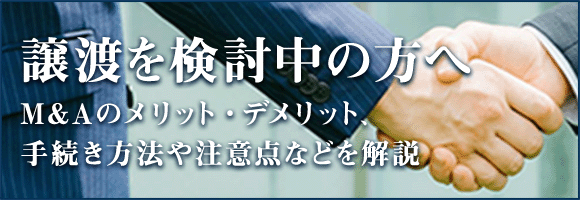税理士事務所・会計事務所のM&A 費用・相場や動向、注意点を徹底解説

更新日:

- この記事の監修者
- フェイス税理士事務所
代表税理士 高田 祐一郎
会計事務所と税理士事務所(税理士法人)の違いと現状
会計事務所・税理士事務所・税理士法人の違いは、「組織形態」「経営者(代表者)」「業務内容」の3つの軸で整理できます。税理士事務所は税理士の個人事業で税務に特化、会計事務所は税理士または公認会計士の個人事業で税務に加えコンサルティングや会計監査など幅広い業務を手がけます。税理士法人は法人形態をとり税務に限定されるものの、事業規模は大きい傾向です。
会計事務所とは
会計事務所は、公認会計士や税理士などが中心となって、企業や個人事業主の会計・税務関連の業務を幅広くサポートする事務所です。具体的には、経理や財務諸表の作成、税務申告、決算対策、経営コンサルティングなどを手がける場合が多く、クライアントが抱える「数字」にまつわる課題をトータルで支援します。
特に中小企業や個人事業主にとっては、日常の経理処理から決算・申告まで一貫してサポートしてくれる心強いパートナーとなります。なお、会計事務所と一口にいっても、業務内容は事務所によって異なり、保険代理業や相続対策、開業支援など幅広いサービスを提供するケースもあります。コンサルティング機能を強化している事務所も多く、経営全般のアドバイザーとして活躍する場面が増えているのも特徴です。
会計事務所と税理士事務所の違い
会計事務所と税理士事務所の違いは、経営者(代表者)と業務内容に違いがあります。
税理士事務所は、税理士が個人事業として営んでいる事務所のことです。業務内容は、基本的に税務に限定しています。
一方、会計事務所は税理士または公認会計士が個人事業として営んでいる事務所のことです。会計事務所といっても、税理士事務所と同じように税理士が代表者として経営していることも多いです。
つまり、税理士は税理士事務所もしくは会計事務所として個人事業を営み、公認会計士は会計事務所として個人事業を営みます。会計事務所の業務内容は、税務にとどまらずコンサルティングなどを行うことが多いです。
会計事務所と税理士法人の違い
会計事務所と税理士法人の違いは、組織形態にあります。会計事務所は個人事業であるのに対し、税理士法人は法人です。そのため、事業規模は税理士法人のほうが大きい傾向にあります。また業務内容も、税理士法人は税務に限定していることが多いです。
会計事務所と税理士事務所、税理士法人の違いをまとめると、以下のとおりです。
| 税理士事務所 | 会計事務所 | 税理士法人 | |
|---|---|---|---|
| 経営者(代表者) | 個人 | 個人 | 法人 |
| 業務内容 | 税務 | 税務 コンサル業務 会計監査 |
税務 |
| 組織形態 | 個人事業 | 個人事業 | 法人 |
税理士事務所・会計事務所業界の現状
税理士事務所・会計事務所業界は「高齢化」と「若手不足」の二重苦に直面しています。日本税理士会連合会が2024年に行った「第7回税理士実態調査」によると、60歳代以上が53.6%を占め、最も多い年齢層は「60歳代」の25.7%、次いで「70歳代」の22%という結果でした。さらに深刻なのは70歳代以上が27.9%に上昇している点です(第6回調査では23.7%)。
一方、20~30歳代の若手税理士はわずか6.6%にまで減少し、10年前の第6回調査(10.9%)から約半減しています。開業税理士に限定すると、60~79歳が55.9%を占め、所長1名に依存する小規模事務所では後継者不在による廃業リスクが現実的な脅威となっています。
国税庁の公表データ(国税庁公式サイト)によると、2023年(令和5年)度時点の税理士登録者数は81,280人ですが、税理士試験の受験者数は長期的に減少傾向にあり、ベテラン層の大量引退が今後5~10年で本格化すれば人材不足はさらに加速します。こうした背景から、M&A(合併・買収)を活用して顧客基盤や人材を維持しつつ事業を継続する動きが活発化し、業界再編の波が加速しています。
個人経営の税理士事務所・会計事務所における後継者問題とM&A
個人経営の会計事務所では、所長の高齢化と後継者不在が相まって廃業リスクが深刻化しています。M&Aは「買い手」「売り手」双方にメリットをもたらす解決策です。買い手は既存の顧問先・熟練スタッフをまとめて承継し短期間で組織拡大できる反面、売り手は後継者問題を解決しつつ従業員の雇用を守り、長年築いた事業価値を対価として評価してもらえます。廃業では失われる顧問先との信頼関係やノウハウを次世代に引き継げる点が、M&A最大の価値といえるでしょう。
税理士事務所・会計事務所の後継者問題
個人経営の税理士事務所や会計事務所では、所長1名の高齢化と後継者不在が相まって、廃業の危機が深刻化しています。たとえば、代表税理士と少数のスタッフだけで事務所を切り盛りしている場合、後を継ぐ資格者が確保できなければ、顧問先や従業員の行き先がないまま事業を閉じざるを得ない状況に追い込まれかねません。
さらに、中小企業を取り巻く経済環境の変化や、会計事務所の採用環境の悪化により、業務拡大が難しくなっている事務所も少なくありません。こうした背景から、最近ではM&A(合併・買収)を活用して後継者問題を解決しようとする動きが目立つようになりました。個人経営の会計事務所が自力で後継者を育成・招聘するのが難しい場合、所長が元気なうちにM&Aを通じて事務所の資産と人材をまるごと譲渡する選択肢を検討するのは、ごく自然な流れといえるでしょう。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 引退が近づく所長にとって、事務所運営を支えてくれた顧問先様や従業員はとても大切な存在です。安心できる税理士事務所への承継を望まれています。

- フェイス税理士事務所代表税理士 高田 祐一郎
M&Aで得られるメリット【買い手(譲受側)の場合】
買い手(譲受側)にとって最大のメリットは、既存の顧問先や熟練スタッフをまとめて引き継げる点です。従来の方法であれば、新規営業や採用に多くのコストと時間をかけねばなりません。しかし、M&Aによって安定した収益基盤とノウハウを一括承継できれば、短期間で組織を拡大できる可能性があります。
また、専門分野の拡大や地域進出の手段としてもM&Aは有効です。たとえば、相続税案件や医療系の会計支援など、特定分野に強みを持つ事務所を譲り受ければ、新たな顧客層を獲得しやすくなります。同業同士であるからこそ、経営ノウハウや顧客データの相乗効果も大いに期待でき、結果的に競争力を高めることにつながるでしょう。
M&Aで得られるメリット【売り手(譲渡側)の場合】
一方、売り手(譲渡側)にとっての最大のメリットは、後継者不在問題を一挙に解決できることです。高齢化や人手不足が進むなかで、所長の引退時期に後継者が見つからない場合、事務所の資産—とりわけ顧問先との信頼関係や経験豊富なスタッフ—が失われる危険があります。しかし、M&Aによって経営基盤の整った別の事務所や税理士法人とマッチングできれば、従業員の雇用を守り、顧問先との関係を維持したまま引退を迎えられます。
さらに、長年築いてきた事務所の価値を対価として評価してもらえるため、所長や家族の将来資金を確保できる点も見逃せません。もし「廃業」という選択肢しかなければ、積み重ねてきたノウハウや顧問先との信頼も一切収益化できずに終わってしまいます。したがって、M&Aは経営者の“最後の大仕事”として大きなメリットをもたらしてくれる手法だといえるでしょう。
税理士事務所・会計事務所のM&Aにかかる費用はどれくらいか
会計事務所のM&Aでは、「買収費用」「仲介手数料」「税金」の3つの費用が発生します。買い手は買収費用に加え仲介手数料と消費税・登録免許税を、売り手は譲渡益に対する税金と仲介手数料を負担します。売買価格の相場は税理士業務メインなら年間顧問報酬または年商の1倍程度、コンサルティングなど多角的な業務を手がける場合は時価純資産法やDCF法で企業価値を算出して決定します。
M&Aで売り手・買い手にかかる費用
会計事務所のM&Aでは、仲介手数料・買収費用・税金の3種類が発生します。仲介手数料は売り手・買い手双方に、買収費用は買い手のみに、税金は取引形態によって双方にかかる場合があります。仲介会社によって費用体系は異なるため、契約前に着手金・成功報酬・中間金などの有無を確認してください。
・仲介会社に支払う手数料【売り手側・買い手側】
会計事務所のM&Aを当事者同士が自力で進めることは現実的に難しく、M&A専門の仲介会社と契約して相手を探し交渉するのが一般的です。
仲介会社に支払う費用は「仲介手数料」とよばれ、相談から交渉成立までのいくつかの局面で発生します。仲介会社によって発生する局面は異なりますが、例として以下のような種類の手数料があります。
着手金…仲介会社と契約を結んだ時点で発生する手数料です。着手金は無料のところもあれば、100万円以上必要となる場合もあります。着手金がかかる仲介会社のもとには、M&Aを本気で考えている顧客が集まるというメリットがありますが、M&Aが成立しなくても返金されないので要注意です。
成功報酬…M&Aが成立した時点で支払う手数料です。会計事務所のM&Aにおける成功報酬は、多くの場合10%(最低報酬あり)となります。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 上記以外にも、相談料や中間金(M&Aのプロセスの途中で発生する)、デューデリジェンス費用(買収前に行われる監査)、月額手数料(M&Aが成立するまで毎月支払うもの)が発生することもあります。

- フェイス税理士事務所代表税理士 高田 祐一郎
・買収費用【買い手側】
買い手側には買収費用がかかります。会計事務所の買収価格算出方法については、次項で詳しく説明します。
・税金【売り手側・買い手側】
M&Aで会計事務所を売買した場合、税金がかかる場合があります。たとえば、事業譲渡の手法を用いた場合、売り手側・買い手側それぞれに以下のような税金がかかります。
売り手側…譲渡益に対する税金(売り手が個人なら所得税、法人なら法人税)
買い手側…消費税(譲り受けた資産の中に課税対象のものが含まれる場合)、登録免許税・不動産取得税(不動産を譲り受けた場合)
税理士業務がメインなら年間顧問報酬や年商の総額が相場
個人経営の会計事務所で税理士業務をメインに行っている場合、1年間の顧問報酬または前年の年商が売買価格の相場となります。「税理士業務+α」の収益構造がある場合は年商を基準にします。最終的な売買価格は交渉やデューデリジェンスを経て決定されるため、事前に相場を把握しておくことで適正額の判断ができ、双方納得のいく交渉につながります。
「相続税の申告を多く手がけている」「別法人として設立している会計法人からの記帳代行料がある」「保険代理業の収入がある」などのケースでは、年商を基準にします。

- 記事監修者からの
ワンポイントアドバイス - 実際には交渉やデューデリジェンスを経て最終的な売買価格を決定します。事前に相場を把握しておくことで、適正額の判断ができ、双方納得のいく交渉になることでしょう。

- フェイス税理士事務所代表税理士 高田 祐一郎
コンサルティングなども行っている場合は企業価値を算出する
税理士業務に加えてコンサルティングなどの業務も行っている場合は、「企業価値」をもとに売買価格を決定します。企業価値とは、企業が持つ総合的な価値を表す金額で、事業から生み出される純資産価値・営業権・知的財産価値に加え、預金や遊休地なども含まれます。算出方法は時価純資産法とDCF法の2つが代表的です。
●時価純資産法…企業が保有する有形・無形の資産を時価評価した時価資産から、時価負債を差し引いた「時価純資産」を企業価値とします。
●DCF法…「ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー」の略。フリーキャッシュフロー(会社が自由に使える現金)をもとに企業が将来生み出す価値を出し、そこからコストを割り引いて算出した現在価値を企業価値とします。
税理士事務所・会計事務所をできるだけ高く売却するには
会計事務所の売却を成功させるには、1,000万円〜1億円程度の売上高が必要とされています。売却相場は「1年分の顧問報酬」または「2〜3年分の営業利益」が目安です。たとえば年間顧問報酬4,000万円なら売却価格も4,000万円程度、年間営業利益1,000万円なら2,000〜3,000万円程度で成立します。売却を考え始めたら、まずは売上高の目標額を設定し、数年間のスパンで事業承継計画を作成してください。
税理士事務所・会計事務所の売却相場
売却相場を理解していないと、買い叩かれたり交渉失敗で破談になるリスクがあります。相場は時期や事務所の所在地に左右されますが、「1年分の顧問報酬」または「2〜3年分の営業利益」が基準です。
- 1年分の顧問報酬
- 2〜3年分の営業利益
たとえば1年間の顧問報酬が4,000万円あれば、M&Aも4,000万円程度で成立しやすくなります。また、1年間の営業利益が1,000万円ならば2,000〜3,000万円程度で成立するという計算です。
会計事務所・税理士事務所のM&Aの流れ
M&Aによる事務所の承継では、「事業譲渡」「合併」「持分譲渡」の3つの手法が用いられます。事業譲渡は個人事業向きで譲渡範囲を絞れる反面、契約移管の手続きが多くなります。合併は法人同士が統合し事業規模を拡大できますが、文化やスタッフ間の調整に時間がかかります。持分譲渡は権利移転の手続きがシンプルですが、税理士資格者間での譲渡に限定されます。事務所の規模や代表者の意向、引き継ぎたい業務範囲によって最適な手法を選択してください。
1. 事業譲渡
事業譲渡は、事業全体または一部を丸ごと引き渡す方法です。個人事業の場合、株式のやり取りができないため、従業員や顧問先との契約・設備などを事業単位で譲渡することが主流となります。譲渡する範囲を絞れる一方で、個別に契約の移管作業が必要になる点や、顧問先に対する承諾手続きが多くなる点には注意が必要です。
2. 合併
合併は、複数の法人格を統合して1つの法人にする手法で、税理士法人や会計法人など法人組織の事務所同士で用いられます。
吸収合併の場合は片方の法人が存続し、もう一方は消滅する形で統合されます。
新設合併であれば新しい法人を新設し、両法人を一本化します。
いずれも事業規模が拡大してブランド力や組織体制を強化しやすくなる反面、統合後の文化やスタッフ間の調整には時間がかかる場合があります。
3. 持分譲渡
持分譲渡は、税理士法人の持分を譲渡し所有権を移転する手法です。株式譲渡に近いイメージですが、税理士法人は「社員(出資者)=税理士の有資格者」であることが前提となるため、その範囲で譲渡が行われます。合併や事業譲渡と比べて権利移転の手続きがシンプルなケースが多いものの、買い手・売り手の税理士資格や社員間の合意が必要になる点に留意してください。
会計事務所・税理士事務所のM&A成功事例
会計事務所のM&Aには、「緊急譲渡」「戦略的統合」「家族の理解」「一部譲渡」の4つのパターンがあります。急病による緊急譲渡では地域密着型の顧客基盤を活かした支店化、全国展開を目指す大手による地方拠点の統合、家族の同意を丁寧なコミュニケーションで得た大型案件、スタッフ退職をきっかけとした一部譲渡など、事務所の状況や譲受側の戦略によって最適な手法が異なります。譲渡額は年商の0.8〜1.6倍程度で成立しており、M&A実績が豊富な譲受側ほど円滑な統合が実現しています。
事例1:急病による緊急譲渡から支店化へのスムーズな移行
愛媛県で年商6,200万円規模のJ会計事務所(従業員4名)では、64歳の所長の突然の病気をきっかけに、同県内の税理士法人への譲渡を実現しました。
【背景】
所長夫妻で運営していた事務所でしたが、所長の急病により事業継続が困難な状況に直面。奥様は業務継続の意向が強く、早急な対応が必要でした。
【承継プロセス】
愛媛県内の年商1.5億円規模のM税理士法人(従業員21名)の支店として受け入れる形で、譲渡額5,000万円での事業譲渡が実現。44歳の所長が率いるM税理士法人の支店として、自宅兼事務所の形態を維持したまま、従来の業務スタイルを継続することができました。
【成功ポイント】
急な事態にも関わらず、地域密着型の事務所として培ってきた顧客基盤を活かしつつ、支店化による安定的な経営体制を構築できた点が、関係者全員にとってのメリットとなりました。
事例2:全国展開を目指す事務所による地方拠点の戦略的統合
岡山県の年商4,400万円規模のS税理士事務所(従業員8名)が、大阪府の大手会計事務所グループの一員となった事例です。
【背景】
72歳の所長が後継者不在に悩む一方、譲受側のG会計事務所(年商4億円、従業員40名)は過去3拠点のM&A実績を持ち、さらなる展開地域の拡大を目指していました。
【承継プロセス】
双方の意向が合致し、譲渡額3,820万円での譲渡が成立。68歳の所長が率いるG会計事務所の豊富なM&A実績が、円滑な統合の決め手となりました。
【成功ポイント】
譲受側の複数拠点展開の実績と統合ノウハウが、地方事務所の円滑な承継を可能にした好例といえます。
事例3:丁寧なコミュニケーションが実現した大型案件
三重県の年商7,000万円規模のM税理士事務所(従業員12名)が、愛知県の大手税理士法人への譲渡を実現した事例です。
【背景】
65歳の所長は後継者不在に悩んでいましたが、奥様の同意を得ることが大きな課題でした。一方、譲受側の税理士法人H(年商15億円、従業員120名)は、営業エリア拡大を目指していました。
【承継プロセス】
当初は進展が難しい状況でしたが、奥様と譲受側の59歳の所長との直接対話を通じて信頼関係を構築。譲渡額8,000万円での合意に至りました。
【成功ポイント】
経営理念への共感と魅力的な報酬条件の提示に加え、特に家族の理解を得るための丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となりました。
事例4:一部譲渡による事業規模の最適化
神奈川県の年商5,000万円規模のU会計事務所が、事業の一部を東京都の税理士法人に譲渡した柔軟な対応事例です。
【背景】
53歳の所長は、重要スタッフの退職をきっかけに事業規模の見直しを検討。一方で、自身は継続して事務所経営を行いたいという意向を持っていました。
【承継プロセス】
年商7億円規模の税理士法人D(従業員74名)に対し、退職スタッフが担当していた顧問先のみを譲渡額8,000万円で譲渡。U会計事務所は3名体制で事業を継続しています。
【成功ポイント】
事業全体の譲渡ではなく、一部譲渡という柔軟な手法を選択したことで、双方にとって最適な解決策を見出すことができました。
M&A成功のための注意点・ポイント
M&A成功には、「アドバイザー選定」「早期準備」「顧客契約リスク対策」の3つが重要です。会計事務所のM&A経験が豊富なアドバイザーを選び、相手先探しに数年かかることを想定して早めに準備を開始してください。最大のリスクは顧問先との契約解消で、代表税理士が譲渡後もしばらく籍を置いて顧問先に丁寧に説明することで解約を防げます。会計事務所のM&Aでは、こうした事業・経営の統合プロセス(PMI)を設けることが一般的です。
信頼できるアドバイザーを選ぶ
会計事務所のM&Aは一般企業と事業形態が異なるため、会計事務所・税理士事務所の業務に精通したアドバイザーを選ぶ必要があります。M&A経験が豊富で、業界特有の手続きや交渉に対応できるアドバイザーに依頼してください。
M&Aは相手先との交渉や手続きなど専門知識が必要なため、M&Aアドバイザーに業務を依頼するのが一般的です。会計事務所や税理士事務所の業務に精通していないアドバイザーでは、業界特有の課題に対応できずうまくいかない場合があります。
早い時期からM&Aの準備を進める
M&Aはアドバイザーへの相談からクロージングまで、相手先探しだけで数年かかる場合があります。後継者不在や引退年齢が決まっている場合は、早い時期からM&Aの準備を進めてください。
相手先がすぐに見つかるとは限らず、引退したいからといって直ちにM&Aができるわけではありません。準備開始が遅れると引退が先延ばしになることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
M&Aにより顧客との契約が解消されるリスクを考慮する
会計事務所のM&Aで最大のリスクは、顧問先が譲渡先との契約を嫌がり解約する可能性です。代表税理士が譲渡後もしばらく籍を置いて顧問先に丁寧に説明することで、契約解消リスクを減らせます。
顧問先が譲渡先の会計事務所や税理士事務所との顧問契約を嫌がって、契約を解約する可能性があります。代表税理士がM&Aで事業を譲渡した後、譲渡先にしばらく籍を置いて、顧問先にM&Aについて丁寧に説明することで契約解消のリスクを減らせます。会計事務所・税理士事務所のM&Aでは、こうした事業・経営の統合プロセス(PMI)を設けることが一般的です。
事業承継・引継ぎ補助金を活用して経費の削減を
「事業承継・引継ぎ補助金」は、M&Aにかかる費用を最大600万円まで補助する中小企業庁の制度です。売り手・買い手ともに「専門家活用事業」(補助率2/3、上限600万円)を活用でき、M&A仲介会社への手数料やデューデリジェンス費用などが対象となります。申請が必要で、要件は年度ごとに変更される可能性があるため、最新情報は事業承継・引継ぎ補助金公式サイトで確認してください。
補助金には以下の3タイプがあります。
①経営革新事業
M&Aや事業承継をきっかけに、事業の再構築や経営統合などに挑戦する際の費用を補助。
補助率2/3、補助上限額600万円
②専門家活用事業
M&Aにかかる専門家などの活用費用(M&A仲介会社への手数料、デューデリジェンス費用など)を補助。
補助率2/3、補助上限額600万円
③廃業・再チャレンジ事業
再チャレンジを目的に既存事業を廃業するための費用を補助。
補助率2/3、補助上限額150万円
会計事務所のM&Aで売却する場合、②専門家活用事業を売り手・買い手のどちらも活用可能です。
記事監修者 高田税理士からのワンポイントアドバイス
高齢を迎えた所長の最後の仕事として、長年お世話になってきた顧問先様、家族に近い従業員を、安心して任せられる事務所へ承継し、引退したいと考えるものです。しかし、思いに共感してくれる承継先、しっかりとした組織を持つ税理士法人を見つけることはなかなか困難です。
そこで、M&Aを活用すれば、事業拡大を目指す税理士事務所とマッチングする機会を増やすことができるため、承継の手法として使われる機会が増えてきています。
まとめ
会計事務所・税理士事務所の後継者問題は、M&Aによって顧問先・従業員・事業価値の3つを守りながら解決できます。売却相場は年間顧問報酬または年商の1倍程度、譲渡額は1,000万円〜1億円が目安です。M&A成功には、会計事務所の業務に精通したアドバイザーを選び、相手先探しに数年かかることを想定して早めに準備を開始し、代表税理士が譲渡後もしばらく籍を置いて顧問先に丁寧に説明することで契約解消リスクを減らすことが重要です。
事業承継・引継ぎ補助金(最大600万円)を活用すれば、M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用を抑えられます。廃業では失われる顧問先との信頼関係やノウハウを次世代に引き継ぎ、従業員の雇用を守り、事業価値を対価として評価してもらえるM&Aは、所長にとって「最後の大仕事」といえるでしょう。後継者不在や引退年齢が決まっている場合は、早い時期から会計事務所のM&A経験が豊富な専門家に相談してください。
よくある質問
Q1. 会計事務所のM&Aにかかる費用はどれくらいですか?
買収費用に加え、売り手・買い手ともに仲介手数料(成功報酬10%が一般的)がかかり、税金は事業譲渡の場合、売り手に譲渡益への所得税または法人税、買い手に消費税・登録免許税が発生します。
Q2. 会計事務所の売却相場はどのように決まりますか?
税理士業務がメインなら1年分の顧問報酬または前年の年商、コンサルティングなど多角的な業務を手がける場合は時価純資産法やDCF法で算出した企業価値が基準となります。
Q3. 会計事務所のM&Aにはどのような手法がありますか?
事業譲渡(個人事業向き、契約移管の手続きが多い)、合併(法人同士の統合、事業規模拡大)、持分譲渡(税理士資格者間での譲渡、手続きがシンプル)の3つの手法があります。
Q4. M&Aの準備はいつから始めるべきですか?
相手先探しだけで数年かかる場合があるため、後継者不在や引退年齢が決まっている場合は早い時期から準備を開始し、余裕を持ったスケジュールで進めてください。
Q5. M&Aで売り手側にはどのようなメリットがありますか?
後継者不在問題を解決しつつ従業員の雇用を守り、顧問先との関係を維持したまま引退でき、長年築いた事業価値を対価として評価してもらえるため所長や家族の将来資金を確保できます。

- この記事の監修者
- フェイス税理士事務所
代表税理士 高田 祐一
カテゴリから探す
人気記事ランキング
おすすめページ
M&A相談センターについて