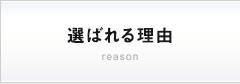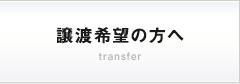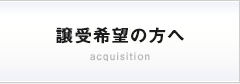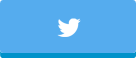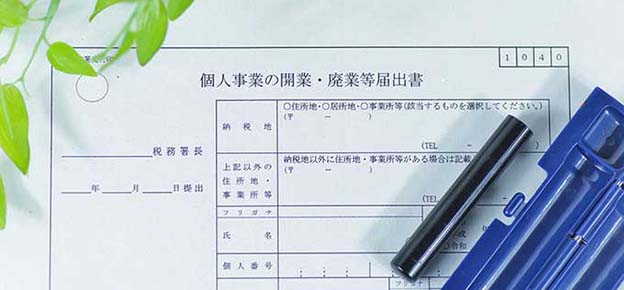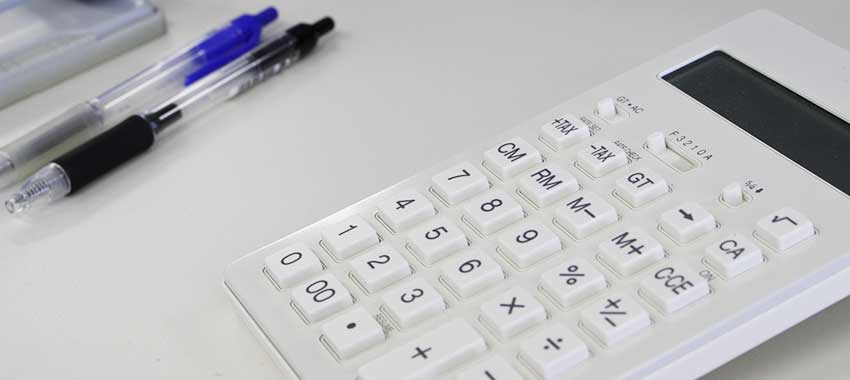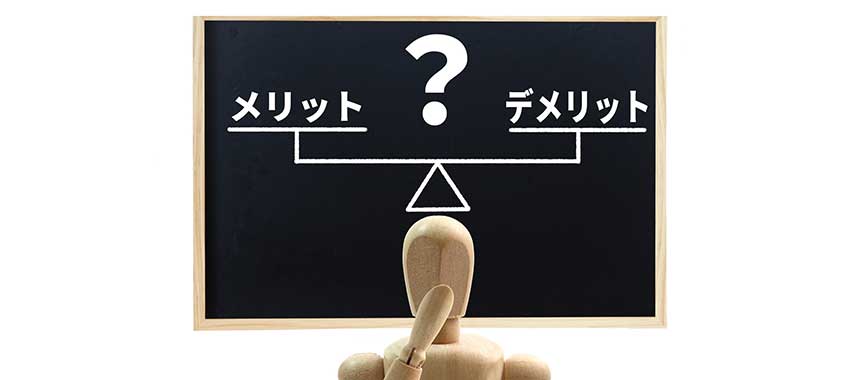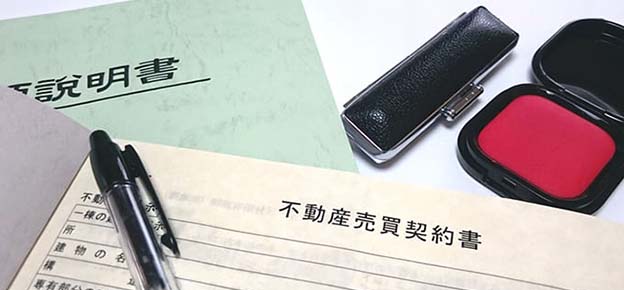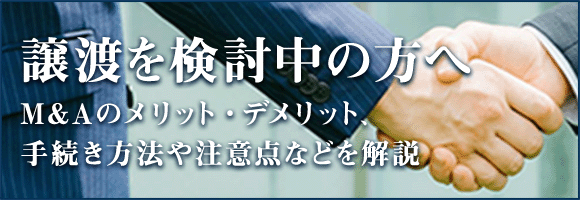M&Aの目的とは? 売り手と買い手に分けてわかりやすく解説!

更新日:
■売り手側におけるM&Aの目的
会社や事業を売却したい側のM&Aの目的は次のとおりです。
後継者問題の解決
多くの日本企業は、後継者がいないといわれています。後継者が現れなければ、現経営者は退任できません。だからといって、後継者不在の状態で経営を続けていると、病気や怪我で急遽退任することになった際に、会社の経営が立ち行かなくなる恐れがあります。
病気や怪我のリスクは高齢になるほどに上がるとされているため、早い段階から後継者を探しておくことが重要です。しかし、身内や従業員の中に、後継者にふさわしい人物がいるとは限りません。
そこで、M&Aで第三者に会社を引き継ぐことで、後継者問題が解決します。
資金調達
会社や事業を売却して、新しい会社や事業を立ち上げるために必要な資金を調達する方法があります。新しい会社や事業を立ち上げた結果、現在経営している会社に割ける労力が少なくなる場合は、M&Aで売却するのも1つの選択肢です。
新規事業を立ち上げて、事業の将来性の評価が高くなったタイミングで売却して、また新たに事業を立ち上げる人も少なくありません。創業期のM&Aは事業の将来性を評価して譲渡価額が決まるため、評価次第で多額の資金を調達できます。
不採算事業の排除
採算がとれていない事業にリソースを割かれている場合は、売却を検討してはいかがでしょうか。複数の事業を展開している場合、赤字の事業が1つでもあると会社全体の収益性の評価に影響を及ぼします。
金融機関から融資を受けるときに不採算事業に注目されてしまうと、融資額が減る恐れもあります。つまり、会社全体で利益が出ていても、不採算事業を抱えていることはリスクと言えるのです。
また、不採算事業を売却して得た利益は、黒字事業に投入できるため、さらなる収益アップに繋がるでしょう。
経営が厳しい企業の存続
会社の存続が危ぶまれる状況では、利益を増やすために新事業を立ち上げたり新たな施策を講じたりする必要があります。しかし、状況が好転しないまま倒産に至るケースは少なくありません。倒産すると、従業員は全員解雇することになり、従業員とその家族が路頭に迷う恐れもあります。
そこで、経営が厳しく状況の好転が期待できない場合にM&Aを実行することで、従業員の雇用を守れる可能性があるのです。
■買い手側におけるM&Aの目的
続いて、M&Aで会社や事業を譲受する側の目的について、詳しくみていきましょう。
技術の獲得
新しい領域への参入を検討している場合、技術やノウハウの獲得が大きな課題となります。すでに、その領域で事業を展開している会社とM&Aを行うことで、技術やノウハウを獲得できるのです。そのため、新しい領域で事業をスピーディーに展開できるようになります。
事業の強化
売り手企業を買収することで、自社の事業が発展し、より多くの収益を得られるようになる場合があります。このような相乗効果のことをシナジー効果といいます。例えば、卸売業が流通業を買収すると、流通コストを大幅に削減できるでしょう。結果的に利益率が増えて収益拡大に繋がります。このように、M&Aを行うときはシナジー効果を得られる企業・事業を選ぶことが重要です。
経営基盤の強化
同業他社を買収すると、経営基盤が強固なものになります。経営基盤の強化には、人材の採用や新しいノウハウ・技術の獲得が必要です。しかし、短期間で経営基盤を強化することは困難でしょう。そこで、他社の人材やノウハウ・技術を獲得できれば、迅速かつ効率的に経営基盤を強化できるのです。
優秀な人材の確保
優秀な人材は、企業の収益力に大きく関わるため、常に採用を目指したいところです。自社の従業員にはないスキルを持つ人物をM&Aで獲得できれば、収益力や安定性の向上が期待できます。ただし、引き続き自社で働くかどうかは売り手の従業員が自由に選べるため、必ずしも優秀な人材を確保できるとは限りません。
海外への進出
グローバル化を推進している場合、海外の企業を買収することで速やかに海外進出を実現できます。また、すでにグローバル化を果たしている企業を買収した場合も、海外進出ができるでしょう。そのほか、進出先の国と強いコネクションがある人物や、外国語が堪能な人物を獲得できた場合も、海外進出が加速します。
シェアの拡大
同業他社を売却することでシェア率が高まるため、さらなる収益アップに繋がるでしょう。シェア率が上がると自社の知名度も上がり、世間からの信頼性が高まります。また、業界シェアが高い企業は、他の企業からも信頼性が高いため、受注数が増えたり単価が上がったりする可能性もあります。
■M&Aの種類
M&Aには、株式譲渡や事業譲渡など、さまざまな種類があります。それぞれの違いを踏まえ、自社に適した方法を選びましょう。
株式譲渡
株式譲渡は、株式を相手に譲り渡すことで経営件を引き継ぐ手法です。事業単位ではなく、会社全体を譲渡することになるため、目的が後継者不足や資金調達の場合に適しています。また、株式譲渡は株式譲渡契約を締結して、買い手が売り手に株式の対価を支払い、株式名簿を書き替えるだけで完了します。
株式譲渡は負債も引き継がれるため、事前にデューデリジェンスで簿外債務の把握が必要です。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の一部あるいは全ての事業を売却する方法です。対象は、商品や工場、不動産、ノウハウ、人材、ブランド、特許権、取引先との関係など多岐に渡ります。一部の事業のみ譲渡できるため、不採算事業を処分したい場合に適しています。
また、買い手は自身が求める従業員や取引先との関係などに絞って譲受できますが、売り手との交渉が必要です。
株式交換
株式交換とは、全ての発行済株式を他社に引き継がせ、親子会社関係を作る方法です。株式の持分比率次第で、子会社は親会社の経営に参画できます。また、一定要件を満たすと、株式を売却したときに得た利益に税金がかかりません。
合併
合併とは、2つ以上の会社が1社になることです。吸収合併と新設合併があります。吸収合併とは、1社のみが存続し、他の会社は消滅して権利義務を存続会社に承継させる方法です。つまり、存続会社は他の会社の財産を全て引き継ぎます。
新設合併は、全ての会社が消滅し、同時に1社が設立されて全ての会社の権利義務を承継する方法です。株式譲渡と比べて関係性が深くなるため、シナジー効果が高くなることが期待できます。
ただし、人事評価の方法や経理処理などを一本化するのに時間と労力がかかります。また、株主総会の特別決議や契約書の備置など、さまざまな手続きが必要です。
■まとめ
M&Aの目的を見据えて準備を進めることで、得られるメリットが大きくなります。後継者問題を解決したい場合は、自社との相性がよい企業を見つける必要があります。シナジー効果を求めるのであれば、売り手と自社との関係性や相性、M&A後のビジネスモデルなどを事前に確認し、慎重に検討したいところです。目的に応じて手法を適切に選び、M&Aアドバイザーや仲介会社のサポートを受けながらM&Aを進めましょう。
カテゴリから探す
人気記事ランキング
おすすめページ
M&A相談センターについて