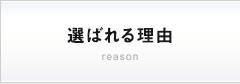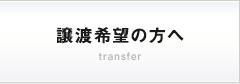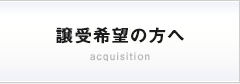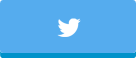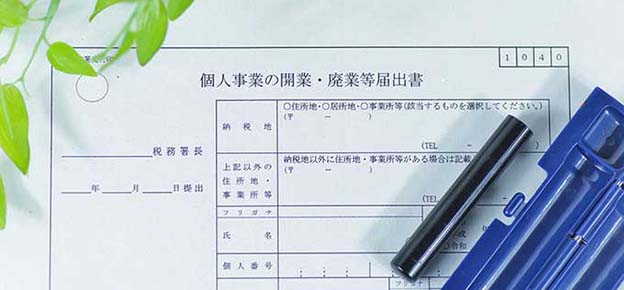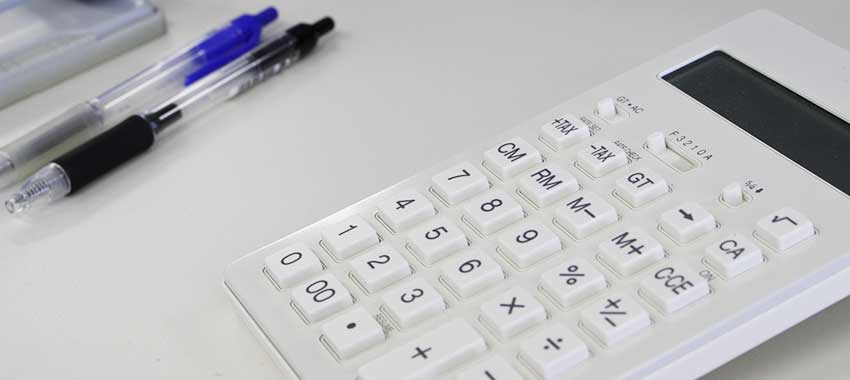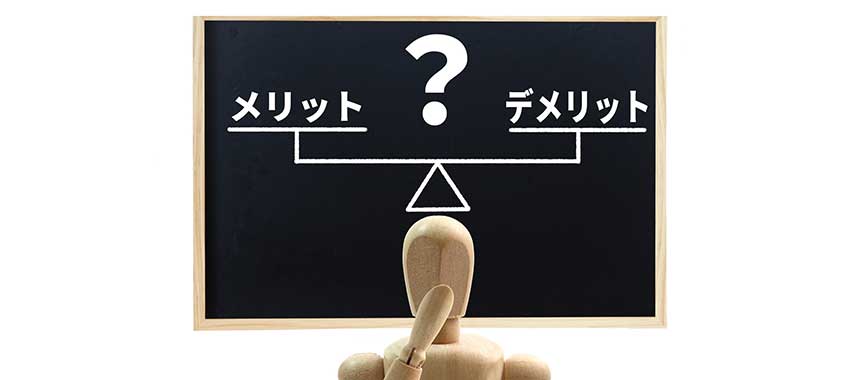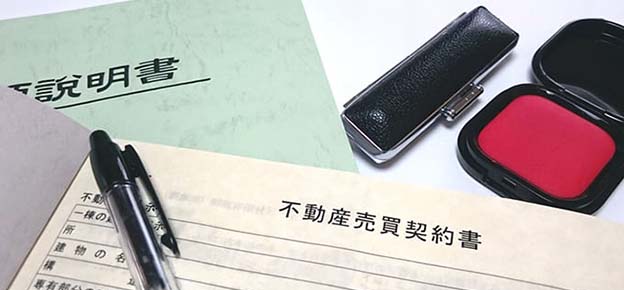税理士を引退したい。後継者不在なら廃業?M&Aの選択肢も

更新日:
税理士が引退を迫られる時代背景と深刻化する課題
税理士が引退を考える決定的なタイミングと理由
税理士の引退を考える理由は多岐にわたりますが、最も多いのは年齢と健康上の問題です。税理士の高齢化は深刻で、日本税理士会連合会の第6回税理士実態調査によると、60代が30.1%、70代が13.3%、80代が10.4%を占め、60歳以上の税理士が全体の54%に達しているという現状があります。
主な引退理由として以下が挙げられます。
健康面での不安が最も切実な問題となっています。長年にわたる激務により体調を崩し、継続的な業務が困難になるケースが増加しています。特に確定申告時期の過重労働は、心身に大きな負担をかけています。
後継者不足も深刻な課題です。親族に税理士資格者がいない、従業員に事業を継がせるには負担が大きすぎる、といった理由で後継者が見つからない事務所が急増しています。
経営環境の悪化も見逃せません。顧問先企業の減少、報酬単価の下落、新規開拓の困難さなどにより、事業の継続が難しくなっているケースも多く見られます。
激変する税理士業界の現状と将来への不安
税理士業界は急速な変化の真っ只中にあります。デジタル化の波により、従来の業務が大きく変わりつつあります。
会計ソフトの高度化により、記帳代行などの基本業務は自動化が進み、付加価値の高いコンサルティング業務への転換が求められています。しかし、長年同じスタイルで業務を行ってきた税理士にとって、この変化への対応は容易ではありません。
競争の激化も避けられない現実です。税理士資格者数は増加している一方で、中小企業の数は減少傾向にあり、一人当たりの顧問先獲得が困難になっています。
顧問料の相場下落も経営を圧迫しています。インターネットを通じた格安サービスの登場により、従来の報酬体系では競争力を保てなくなっているのが実情です。
引退を決断する前に検討すべき重要なポイント
引退を考える前に、まず現状を客観的に分析することが重要です。「本当に引退が最善の選択なのか」を冷静に判断する必要があります。
事業の現状分析では、顧問先の安定性、収益性、将来性を詳細に検討します。一時的な困難なのか、構造的な問題なのかを見極めることが大切です。また、事業承継という選択肢についても検討が必要です。会計事務所・税理士事務所の事業承継の流れや成功させるためのポイントについては、こちらで詳しく解説しています。
改善の余地についても検討が必要です。業務効率化、サービスの差別化、新たな顧客層の開拓など、現状を打開する方法がないかを探ってみましょう。
家族や従業員への影響も重要な判断材料です。引退により影響を受ける人々への責任も考慮する必要があります。
税理士引退時の4つの選択肢とそれぞれの特徴
税理士が引退する際の選択肢は大きく4つに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の状況に最も適した方法を選択することが重要です。
選択肢1:廃業
廃業とは、事務所を完全に閉鎖し、すべての業務を終了する方法です。
廃業のメリット
- 手続きが比較的簡単で迅速
- 引退後の責任や義務から完全に解放される
- 資産処分により一定の現金を確保できる場合がある
廃業のデメリット
- 事業価値を一切回収できない
- 顧客に新しい税理士を探す負担をかける
- 従業員の雇用が失われる
- 長年築いてきた信頼関係が断絶される
廃業に向いているケース
- 顧問先が少なく従業員もいない小規模事務所
- 健康上の理由で急を要する場合
- 後継者候補が全くいない状況
選択肢2:親族承継
親族承継とは、配偶者、子ども、親族などに事業を引き継ぐ方法です。
親族承継のメリット
- 家族内で事業を継続できる安心感
- 顧客との関係を維持しやすい
- 段階的な引き継ぎが可能
- 事業価値を適正価格で承継できる
親族承継のデメリット
- 後継者に税理士資格が必要
- 経営能力や顧客との相性に課題がある場合がある
- 準備期間が長期間必要
- 家族間のトラブルのリスク
親族承継に向いているケース
- 税理士資格を持つ親族がいる
- 後継者に経営意欲と能力がある
- 顧客からの信頼を得られる人物がいる
選択肢3:従業員承継
従業員承継とは、事務所で働く従業員に事業を譲渡する方法です。
従業員承継のメリット
- 事務所の文化や業務スタイルを継続できる
- 顧客との関係が維持しやすい
- 従業員のモチベーション向上
- 事業価値を適正価格で回収できる
従業員承継のデメリット
- 従業員の資金調達が最大の課題
- 経営者としての能力開発が必要
- 責任の重さに従業員が躊躇する場合がある
- 準備期間が長期間必要
従業員承継に向いているケース
- 優秀で信頼できる従業員がいる
- 従業員に経営意欲がある
- 資金調達の目処が立つ
選択肢4:第三者承継(M&A)
第三者承継とは、同業他社や投資家などの第三者に事業を売却する方法です。
第三者承継のメリット
- 事業価値を適正に評価し現金化できる
- 顧客・従業員の雇用継続が期待できる
- 後継者探しの心配がない
- 比較的短期間で完了できる
第三者承継のデメリット
- 買い手探しに時間がかかる場合がある
- 事務所の文化が変わる可能性
- 顧客の一部が離れるリスク
- 仲介手数料などのコストが発生
第三者承継に向いているケース
- 一定規模以上の顧客基盤がある
- 収益性が安定している
- 従業員が複数いる
- 親族・従業員承継が困難
各選択肢の具体的な進め方と注意点
廃業の進め方と手続きのポイント
廃業の基本的な流れ
- 廃業時期の決定と計画策定(6ヶ月前)
事業終了時期を決定し、顧客や従業員への影響を最小限に抑える計画を立てます。 - 顧客への事前通知(3ヶ月前)
顧客に対して廃業の旨を正式に通知し、新しい税理士の紹介や引き継ぎについて説明します。 - 従業員への対応(3ヶ月前)
従業員への十分な事前通知と転職支援を行います。 - 必要書類の整理と引き継ぎ
顧客の重要書類を整理し、新しい税理士への引き継ぎを円滑に行います。 - 各種手続きの実施
税理士会への廃業届提出、税務署への各種届出、事務所の解約手続きなどを行います。
廃業時の注意点
- 顧客への十分な説明責任を果たす
- 機密情報の適切な処理
- 未完了業務の責任ある処理
承継(親族・従業員)の進め方と成功のコツ
承継の基本的な流れ
- 後継者の選定と意思確認(3-5年前)
適切な後継者候補を見極め、承継への意思を確認します。 - 段階的な業務移譲(2-3年前)
重要な顧客との関係構築と業務スキルの向上を図ります。 - 事業価値の評価(1年前)
公正な価格で承継するため、事業価値を適正に評価します。 - 正式な承継手続き
法的な手続きを完了し、顧客・従業員に正式発表します。 - サポート期間の設定
承継後も一定期間のサポートを行い、円滑な移行を確保します。
承継成功のコツ
- 十分な準備期間の確保
- 後継者の能力開発への投資
- 顧客との信頼関係構築
- 段階的な権限移譲
事業譲渡(M&A)の進め方と成功のポイント
事業譲渡の基本的な流れ
- 事前準備と現状分析(6ヶ月前)
事業価値を正確に把握し、売却に向けた準備を整えます。 - 譲渡仲介会社の選定
税理士業界に精通した信頼できる仲介会社を選択します。 - 買い手候補の選定
複数の候補から最適な買い手を選定します。 - 交渉と契約締結
価格だけでなく、従業員の処遇や顧客対応についても詳細に協議します。 - 引き継ぎとアフターフォロー
計画的な引き継ぎにより、顧客満足度を維持します。
事業譲渡成功のポイント
- 適切な仲介会社の選択
- 事業価値の正確な把握
- 複数候補との比較検討
- 契約条件の詳細な確認
税理士事業譲渡成功事例・実際のケーススタディ
多くの税理士が直面する「後継者がいないが廃業はしたくない」という課題に対して、事業譲渡(M&A)がどのような解決策となるかを具体的な成功事例で見てみましょう。廃業や親族承継については比較的進め方が明確ですが、事業譲渡については「実際どうなるのか」が最も気になるポイントのため、ここでは譲渡事例に焦点を当てて詳しく解説します。
事例1:埼玉県T会計事務所→Z税理士法人(譲渡額9,000万円)
T会計事務所の概要
| 所在地 | 埼玉県 |
| 従業員数 | 8名 |
| 年商 | 1.2億円 |
| 所長年齢 | 74歳 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
Z税理士法人の概要
| 所在地 | 東京都 |
| 従業員数 | 30名 |
| 年商 | 4億円 |
| 所長年齢 | 52歳 |
| 譲受理由 | 事業拡大 |
背景と課題
子どもが税理士にならず、後継者不在で悩んでいたT事務所の所長。74歳という年齢もあり、引退を真剣に検討していました。しかし、長年築いてきた顧客との信頼関係を大切にしたく、「これまでのやり方を変えずに引き継いでほしい」という強い希望がありました。
譲渡成立までの実際の流れ
コーディネーターとの面談を通じて事業価値を適正に評価し、複数の買い手候補との面談を実施。最終的にZ税理士法人との条件が合致し、譲渡が成立しました。
コーディネーターのここがポイント
「子どもや親族に後継者がおらず、年齢的にも引退を考えている」とのご相談をいただきました。長年にわたり顧問先と信頼関係を築いてこられたため、「これまでのやり方を変えずに引き継いでほしい」というご希望がありました。譲受け先となる事務所様と何度も面談を重ねる中で、規模の大きな税理士法人Z様の体制に安心感を持たれ、無事に譲渡が成立しました。
事例2:東京都T税理士事務所→M税理士法人(譲渡額2,700万円)
T税理士事務所の概要
| 所在地 | 東京都 |
| 従業員数 | 4名 |
| 年商 | 3,040万円 |
| 所長年齢 | 81歳 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
M税理士法人の概要
| 所在地 | 東京都 |
| 従業員数 | 68名 |
| 年商 | 4.1億円 |
| 所長年齢 | 58歳 |
| 譲受理由 | 事業拡大 |
背景と課題
家族経営のT税理士事務所は、81歳の所長と家族で運営していました。後継者がいない中で長年事業を継続していましたが、所長の突然の病気により、急遽事業承継の必要に迫られました。年齢も高く、一刻も早い解決が求められる状況でした。
譲渡成立までの実際の流れ
緊急性を考慮し、迅速な事業価値評価と買い手候補の厳選を実施。家族の受け入れ条件も含めて交渉を進め、M税理士法人との譲渡が成立しました。
コーディネーターのここがポイント
譲渡し側のT税理士事務所は所長が81歳。後継者がいない中、ご家族で事務所を経営されていました。所長様はご高齢でありながら経営を続けていらっしゃいましたが、突然のご病気により、事務所をM&Aで譲渡したいと弊社にご相談いただきました。ご希望は、譲渡額だけでなく、一緒に働いてきたご家族がそのまま受け入れられること。譲受先の事務所で実際に見学を行い、その中でM税理士法人様の社内の雰囲気が気に入られ、無事譲渡成立となりました。
事例3:愛媛県J会計事務所→M税理士法人(譲渡額5,000万円)
J会計事務所の概要
| 所在地 | 愛媛県 |
| 従業員数 | 4名 |
| 年商 | 6,200万円 |
| 所長年齢 | 64歳 |
| 譲渡理由 | 急病のため |
M税理士法人の概要
| 所在地 | 愛媛県 |
| 従業員数 | 21名 |
| 年商 | 1.5億円 |
| 所長年齢 | 44歳 |
| 譲受理由 | 事業拡大 |
背景と課題
所長とその奥様で運営していたJ会計事務所。所長の突然の病気により、奥様一人では事務所運営が困難になりました。しかし、奥様は「仕事を続けたい」という強い希望を持っており、単純な廃業ではなく、働き続けられる環境を求めていました。
譲渡成立までの実際の流れ
継続就業を前提とした買い手候補を選定し、支店として受け入れ可能な法人との面談を実施。自宅兼事務所の継続使用も含めた条件で、M税理士法人との譲渡が成立しました。
コーディネーターのここがポイント
所長である旦那様と奥様が2人で運営されていた事務所でしたが、旦那様の突然のご病気をきっかけに、弊社へご相談をいただきました。奥様は仕事を続けたいというご希望をお持ちだったため、支店として受け入れ可能な事業譲渡をご提案。結果として、M税理士法人との譲渡が成立しました。自宅兼事務所はそのままに、これまで通りの形で事務所運営を続けていらっしゃいます。
引退後の充実した人生設計と新たな可能性
税理士引退がもたらす生活の質的向上
引退により得られる最大のメリットは、時間と心身の自由です。長年にわたる激務から解放され、健康的なライフスタイルを取り戻すことができます。
時間的余裕の獲得により、家族との時間を大切にできるようになります。子どもや孫との関係を深めたり、配偶者と旅行を楽しんだりと、これまで仕事で犠牲にしてきた時間を取り戻せます。
ストレスの軽減も大きな変化です。顧問先の問題に常に気を配る必要がなくなり、確定申告時期の過重労働からも解放されます。
健康面での改善も期待できます。規則正しい生活リズムを取り戻し、運動や趣味に時間を割くことで、身体的・精神的な健康を向上させることができます。
税理士経験を活かした多様なセカンドキャリア
引退後も税理士としての経験と知識を活かし、新たなキャリアを築くことができます。
コンサルタント業務では、特定の分野に特化した専門コンサルタントとして活動できます。事業承継、相続対策、国際税務など、深い専門知識を求める企業や個人のニーズに応えることができます。
教育・研修事業も魅力的な選択肢です。大学の非常勤講師、税理士受験指導、企業の社内研修講師など、長年の実務経験を若い世代に伝える役割を担えます。
執筆・メディア活動を通じて、専門知識を広く社会に発信することも可能です。税務関連書籍の執筆、業界誌への寄稿、セミナー講師など、多様な活動があります。
非常勤税理士として、必要な時だけ業務に関わる働き方も選択できます。完全引退ではなく、負担を大幅に軽減しながら専門性を活かし続けることができます。
まとめ・よくある質問と最適な選択への道筋
税理士引退成功の3つの鉄則
1. 早めの準備と計画策定
どの選択肢を選ぶにしても、十分な準備期間を確保することが成功の前提条件です。理想的には引退の3年から5年前から準備を始めることをお勧めします。
2. 関係者への十分な配慮
顧客、従業員、家族など、引退により影響を受ける全ての関係者への配慮を忘れてはいけません。信頼関係を最後まで大切にすることが、円滑な引退につながります。
3. 専門家との連携
税理士業界の特性を理解した専門家のサポートを受けることで、より良い結果を得ることができます。一人で悩まず、適切なアドバイスを求めることが重要です。
よくある質問と回答
Q: どの引退方法が最も良いのでしょうか?
A: 最適な選択肢は個人の状況により異なります。事務所の規模、後継者の有無、健康状態、経済的な事情などを総合的に判断する必要があります。
Q: 事業譲渡の場合、どのくらいの価格で売却できますか?
A: 一般的には年間売上の0.5倍から2倍程度が相場とされていますが、顧客の質、継続性、収益性などにより大きく変動します。
Q: 引退後も税理士として働くことはできますか?
A: はい、非常勤税理士として部分的に業務を継続したり、コンサルタントとして活動したりすることが可能です。
引退相談のご案内
M&A相談センターでは、税理士の引退に関する包括的なサポートを提供しています。事業譲渡に限らず、廃業、親族承継、従業員承継など、あらゆる選択肢について中立的な立場からアドバイスいたします。
29年の実績と豊富なネットワークを活用し、お客様の状況に最適な引退プランを一緒に考えさせていただきます。どの選択肢が良いか迷われている方、具体的な進め方を知りたい方は、まずは無料相談をご利用ください。
あなたの理想的な引退と、新しい人生のスタートを全力でサポートいたします。
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “どの引退方法が最も良いのでしょうか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “最適な選択肢は個人の状況により異なります。事務所の規模、後継者の有無、健康状態、経済的な事情などを総合的に判断する必要があります。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “事業譲渡の場合、どのくらいの価格で売却できますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “一般的には年間売上の0.5倍から2倍程度が相場とされていますが、顧客の質、継続性、収益性などにより大きく変動します。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “引退後も税理士として働くことはできますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “はい、非常勤税理士として部分的に業務を継続したり、コンサルタントとして活動したりすることが可能です。”
}
}
]
}
- « 前の記事
カテゴリから探す
人気記事ランキング
M&A相談センターについて