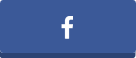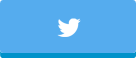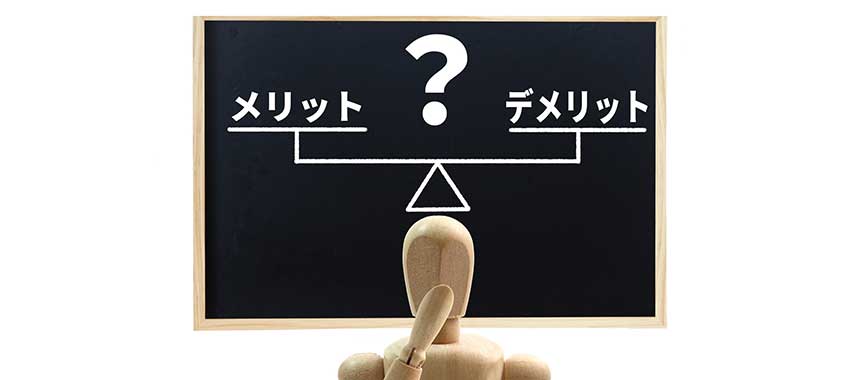M&A案件の成功と失敗(不成功)は、どこで分かれるのか?
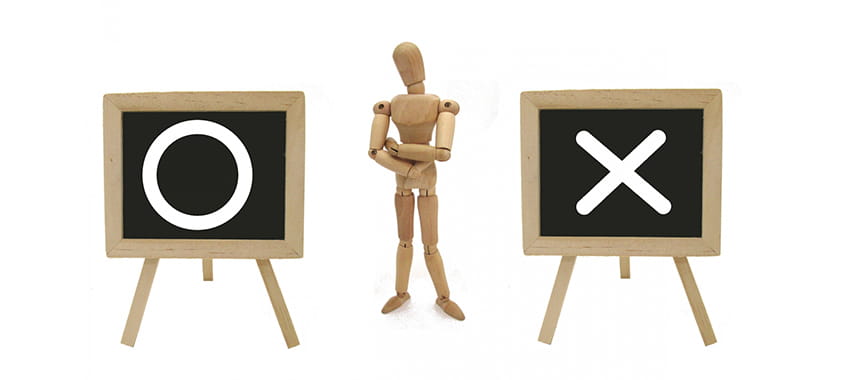
更新日:
■M&A、成功と失敗の境界線
M&Aが成功するかどうかは、ほとんどの場合、「準備をどれだけ丹念に進めてきたか」で決まっていきます。つまり、失敗を避けるために、その根本要因を丁寧に取り除き、時間と費用を掛けて慎重に進めれば進めるほど、M&Aはおのずと成功しやすくなっていくのです。
M&Aの失敗を引き起こしうる要因は主に、「人的」な要因と「経済的」な要因にわかれます。
M&A失敗の人的要因
M&Aが失敗してしまう人的要因としては、「次期経営者」に問題がある場合と、「従業員同士」の相性や関係性が良好でない場合とがあります。経営陣に問題があるのが明らかな場合は、株主総会などで入れ替えも可能です。ただ、M&Aをした複数の会社の従業員同士が融和を図れない場合、その修復は困難を極めます。「うちの会社のやり方に従わない」「前の経営者のほうが良かった」など、感情的なしこりが残ったままのM&Aは、いい結果を生みません。そのような反発的な従業員を不満分子として、解雇や配置転換などに追い込めば、ますます対立は深刻化するおそれがあります。よって、M&Aの準備段階で納得と理解を得られるよう、全従業員に向けて丁寧に説明や質疑応答を繰り返す必要があります。
M&A失敗の経済的要因
M&Aによって、買収をした側が、買収された会社の経済的価値を高く見積もりすぎていたことが、後になって判明する場合があります。もともと優秀な会社を買い取ったのであれば、M&A時の金銭的負担が相対的に重くても、後で収益性を向上させて挽回できるでしょう。しかし、買収された側の会社が深刻な瑕疵・欠陥を(故意または過失により)隠したままM&Aを決めてしまった場合、後からでは取り返しの付かない結果となるおそれがあります。このほか、政治・経済・文化的な外部要因によって、本来であれば成功しているはずのM&Aが、思うようにうまくいかない結末を迎える場合もありえます。
そのような事態を未然に防ぐためにも、考えうる様々な事情を総合的に取り込んだ上で、デューデリジェンス(M&A対象会社の経済価値を正確に見積もる調査活動)を慎重に進める必要があるのです。
では、中小企業と大企業で、どのようなM&Aの成功・失敗事例がありうるでしょうか。具体的にみていきましょう。
■中小企業のスモールM&A
防衛的・守備的なM&A(事業承継の目的)
法人である会社は、事業が続く限り何世代にもわたって存続させることもできます。ただ、経営者はいつか引退しなければなりません。そこで、次の世代に経営者の座を引き渡す「事業承継」が問題になります。跡継ぎとなる意思がある子孫がいればいいでしょう。ただ、身内に跡継ぎがいない場合は、外部から跡継ぎを迎え入れることができない限り、廃業に至るリスクが高まります。
そこで、他の法人と合併ないし連携するM&Aを事業承継の手段とすることで、現経営者の引退後も事業を継続させられるのです。これは、廃業という最悪の事態を避けるための、いわば防衛的・守備的なM&Aといえるでしょう。
この事業承継M&Aが成功すれば事業は継続され、従業員の雇用も維持されます。また、現経営者は引退後、株式の売却などで確定的な利益を得られ、個人保証等からも解放されるでしょう。
しかし、事業承継を急ぐがあまり、拙速なM&Aが進められれば、従業員同士の融和やデューデリジェンスの正確性が犠牲になり、M&Aが失敗に終わるおそれがあります。
戦略的・発展的なM&A(事業成長の目的)
事業承継目的のM&Aが守備的なら、より発展性を目指して他社とパートナーシップを組む目的のM&Aは、より攻撃的・戦略的なものといえるでしょう。
自社が保有しない卓越したノウハウや見込み客リストなどをお互いに活かし合い、自社に無かった強みを相互に組み合わせるM&Aです。衰退局面にあった企業が、M&Aを機にV字回復を果たしたり、あるいは売上げ目標の達成期間を大幅に短縮したりすることも可能です。
もっとも、戦略目的のM&Aは、事業承継目的のそれと矛盾するものではありません。事業承継M&Aをきっかけとして、パートナーシップを組んだ複数社の相乗効果が高まることで、前経営者の頃よりも大きく成長していくケースも十分にありうるからです。
また、ベンチャー企業のイグジット手段(創業者や投資家が初期投資を回収する手段)としてもM&Aが注目されています。以前はイグジット目標の主流とみなされてきたIPO(株式新規公開)も、達成件数が年々減っており、国内では年間100件に届かない水準となっています。その厳しさから、多くの監査法人がベンチャー企業のIPO準備を避けようとする傾向もあり、難度がますます高まっているのです。その点、バイアウト(成長した企業ごと他社に買い取らせることで、初期投資を回収する手段)としてのM&Aは、ベンチャー企業のめざすべき、より現実的な中長期目標だといえるでしょう。
■大企業のM&A成功例
中小企業のM&Aは秘密裏に進められ、全貌が外部からは明らかにならない場合があります。一方で、大企業のM&A事例は、報道機関がニュースとして報じるなど、具体的な内容が公開されるケースもあります。こうした例を検討することで、ご自身のかかわるM&Aの成功可能性を引き上げることができるでしょう。
LINEによるファイブの子会社化
2017年 日本最大級のメッセンジャー型SNSを運営するLINE株式会社は、モバイル動画プラットフォームの提供事業を主力とするファイブ株式会社を、およそ51億円で完全子会社化しました。これによりLINEは動画広告事業の強化に成功しています。
ソフトバンクによるボーダフォンの巨額買収
ブロードバンド事業「ヤフーBB」の成功によって勢いづいていたソフトバンクは、携帯電話事業に本格参入するため、2006年、日本市場に参入して間もないボーダフォン社(英国)日本法人を約1兆7,500億円で買収しました。これにより、ソフトバンクは多額の負債を抱えましたが、国内での「3大携帯電話事業」の一角に食い込むことに成功し、さらなる飛躍的な成長を遂げ、日本を代表する企業へと躍り出ました。
■大企業のM&A不成功例
丸紅によるガビロンの買収
国際的にはそれほど名が知られていない丸紅が、アメリカの穀物メジャーの一角、ガビロン社を2013年に買収したニュースは、世界の財界で驚きを持って受け止められました。しかし、このM&Aに警戒した中国が、穀物の中国輸出に制限を掛けたため、国際展開が思うように進まなくなりました。こうした不測の外部要因により、2015年に1,200億円の評価損を出し、丸紅は現在もその「ガビロン後遺症」に喘いでいます。
パナソニックによる三洋電機の買収
パナソニックにおける白物家電事業の強化を目的として、2009年にM&Aが実施されました。これにより、三洋電機の「SANYO」ブランドはいったん消滅しています。ただ、2013年にパナソニックはこのM&Aで6,000億円の評価損を出していることが判明しました。
セブン&アイ・ホールディングスのニッセン買収
2016年、ニッセンが展開していたカタログ販売を取り込む目的でM&Aを実施したセブン&アイ・ホールディングスは、まもなく88億円の営業損失を出してしまいます。カタログ販売は、スマートフォンの普及などにより、すでに年配層の顧客の需要にも合わなくなっていることが要因とされます。カタログ販売事業とセブンイレブンの店舗との連携もなかなか進みませんでした。
■まとめ
M&Aのようなビジネス上の決断は、一概に「成功」「不成功」と分類できるものではありません。短期的には赤字に悩まされるM&Aでも、長い目でみれば大いなる発展のスタートとなる場合もあります。ただ、M&Aは複数の企業のリソースを組み合わせ「経費節減・時間短縮」を図るものです。よって、M&Aはある程度、短期的に成果をあげることを株主等から要求されるのはやむを得ないでしょう。
カテゴリから探す
人気記事ランキング
おすすめページ
M&A相談センターについて